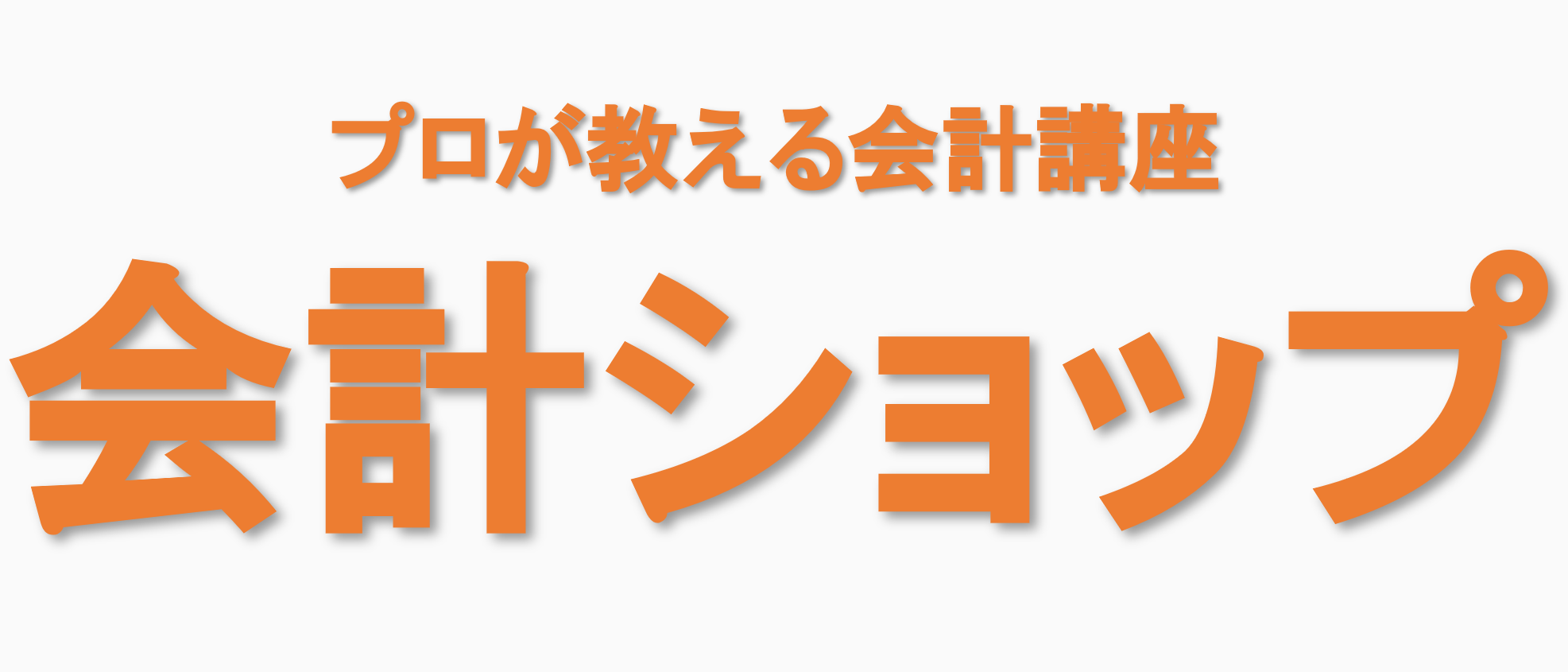転職に活かすために、簿記取得を検討している人も多いかと思います。
一方で、簿記は本当に転職に役立つのか、疑問に思われている人が多いのも事実です。
そこで今回は、簿記が役立つ職業や場面について、具体的に紹介していきます。
1. 簿記で得られる知識

まず、簿記の勉強をすることで得られる知識について、各級ごとに紹介していきます。
1) 簿記3級
簿記3級では、商業簿記の基本的な内容について学びます。
商業簿記とはモノを仕入れて販売するまでの一連の流れを、資産・負債・収益・費用の増減を把握して帳簿に記録することを指します。
製造業などでは2級で学習する工業簿記の知識が必要となりますが、3級で学習する商業簿記が想定するのは製造業以外の一般的な企業です。
3級を学習することで、期中の活動を伝票や試算表に記録し、期末に決算を行う基礎知識を得ることができます。
商売を行う上で大切なモノ・お金の流れのおおまかな全体像を学ぶことができ、2級や1級の土台となる知識となります。
2) 簿記2級
簿記2級では、3級で学んだ内容に加え、より高度な商業簿記の内容や工業簿記について学びます。
商業簿記は3級の各論点について内容を深堀していくだけでなく、本支店会計や連結会計についても学びます。
また、自社で製品を製造する際に必要な工業簿記についても学び、対応できる業種が広がっていきます。
営業活動の流れやコスト管理などについても学ぶことができ、経理以外の職種でも活きてくる知識を身につけることができます。
連結会計や工業簿記など、2級が想定している企業は3級と比べてより規模が大きく複雑な企業となっており、それに対応できる知識を身につけることができるため、簿記2級は高く評価されることが多いです。
3) 簿記1級
簿記1級では、さらに高度な商業・工業簿記の内容や関連法規について学ぶことができます。
そして、経営者や公認会計士・税理士などと会計面において、対等に話すことができる知識を身につけることができます。
ただ、2級と比較して難易度が格段に上がるため、本当に1級まで必要なのか費用対効果を考えながら、検討する必要があります。
2. 転職で有利に働く職業

1) 経理
簿記と聞いて真っ先に思いつく職業である『経理』。
簿記で学べるのはあくまで経理に必要な基礎的な知識であり、より実践的なスキルは実務の中で学んでいく必要があります。
しかし、簿記で学ぶ専門用語は当然のように現場で使われますし、また、土台となる知識なしに実務で1つ1つのことを学んでいっても、全体像がつかめず汎用的ではない知識が身についてしまいます。
そのため経理への転職の際に、簿記2級までの取得を必須としている企業もあります。
経理への転職においては簿記は「持っておいたら有利になる」資格ではなく、「持たないと不利になる」資格と考えておいてください。
経理を目指すのであれば、簿記2級までの取得をおすすめいたします。
【経理への転職体験談】
簿記2級持ちで銀行員から未経験で他社の経理(会計事務所に近い)の仕事に転職しました。
— ひよこ@人見知りブログ (@fszWyNGYhLa1Ypn) July 14, 2021
会社にもよりますが、簿記3級で募集かけてたりする場合もあるので、2級まで持ってるとアドバンテージは大きいです。
当方未経験の20代後半ですが、経理職に強いエージェントさんと面談した際も簿記2級取得後に転職活動に臨むのが理想だと言われ、まずは簿記2級取得に注力しました。実際に面接を受けてみても、簿記2級は経理についてある程度理解している証明になり、志望度も高いと評価されている感触でした。 https://t.co/JOeMxleaVV
— だでぃ@未経験で経理職(元公務員) (@daddy_vt_f) June 25, 2021
転職エージェントを利用するなら、管理部門特化型の中規模エージェントである、以下の3つがおすすめです。
・MS-Japan
・Hupro(ヒュープロ)
・WARCエージェント
ただし、地方求人がないため、地方での転職の場合は大手エージェントのdoda(デューダ)がおすすめです。
詳細は「経理の転職エージェントの選び方とおすすめ4選!」をご確認ください。
2) 会計事務所の事務員
経理と同様に、『会計事務所の事務員』にも、簿記の知識は求められます。
そもそも会計事務所では簿記で学ぶ「会計」が商品となり、簿記を知らないということは一般的な会社で言えば、自社の商品を知らないことと同義となります。
そのため、採用する側も最低限の簿記の知識を要求してきます。
また、会計事務所では公認会計士や税理士の先生方が所長を務めている場合が多く、簿記からのステップアップとして公認会計士や税理士を目指す場合に事務所側の理解を得やすいため、さらなる挑戦を検討している人におすすめの職場と言えます。
3) コンサルタント
『コンサルタント』も簿記の知識が役立つ職業です。
クライアント企業を分析する際に、財務諸表や営業数値を分析する必要があり、それらがどのように作成されたかを把握しておく必要があります。
「この数値は○○と△△を加減して計算しています」といった、各数値の作成過程を現場でいちいち説明することはなく、各数値の成り立ちは当然に知っていることが前提となります。
また、財務デューデリジェンスを行う際にも、財務諸表の各数値に対する知識は当然に求められます。
コンサルタントの場合は財務諸表を作成する知識が得られる簿記だけでなく、財務諸表を読み解く知識が得られる「ビジネス会計検定」の取得もおすすめです。
ビジネス会計検定については「ビジネス会計検定とは?試験の内容をご紹介!」も合わせてご確認ください。
4) 銀行員
『銀行員』も簿記の知識が求められる職業となります。
貸出先企業の経営成績や財政状態をもとに、正常先・要注意先・要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先の区分に振り分けて、貸出を行うか?継続するか?の判断を銀行員は行います。
この際に貸出先企業の各決算書類・財務諸表を見る必要があり、簿記の知識が求められます。
簿記2級までを取得していれば、転職の際に評価される可能性が高いです。
5) 法人営業
意外に思われるかもしれませんが、簿記の知識は『法人営業』にも役立ちます。
法人営業の取引先は法人、つまり企業であり、取引先企業の財務状態を把握して相手先の決済条件を読み、また相手の企業状況を財務情報から読み取り、自社に有利な提案をする必要があります。
この際に簿記の知識が活きてきます。
6) 起業家
最後は転職とは異なりますが、『起業する人』にとっても簿記は有利に働きます。
経営者は売上や利益、資産・負債の構造を当然に把握する必要があるため、簿記で学ぶ知識は必須の知識と言えます。
ただ、起業の場合は簿記という肩書を持っている必要はなく、簿記の学習過程で身につけた知識があれば問題ありません。
そのため極端な話を言えば、受かっていなくても問題ないのです。
3. 転職のこんな場面で役に立つ!

1) 転職先の選定
簿記は転職先企業の情報を得るのに役立ちます。
応募先企業の財務諸表をチェックすることで、今企業がどういった状態で今後のどのような分野に進もうとしているのか?あるいは現状を維持しようとしているのか?といった情報を得ることができます。
その情報を踏まえれば、面接で的外れな回答をする確率がぐっと減ります。
また、応募先企業の財務諸表をチェックして、本当に自分が希望する会社なのか確認することもできます。
チェック項目としては、例えば以下のような項目が考えられます。
・自己資本に対して借入金が異常に多い ⇒ 資金不足を借入でなんとか賄っている。
・福利厚生が充実しているとうたっている割に福利厚生費が少額 ⇒ 実際は福利厚生が充実していない可能性
口コミなどはかなり主観的な情報となりますが、財務諸表の数値は客観的な基準により作成された数値なので、情報の信頼度としては高いです。
2) 書類選考
近年では英語と同様に国際的に活躍するために必要な能力として「会計」に注目が集まっており、簿記の取得はすなわちビジネスの共通言語である「会計」の基礎知識を有していることを意味します。
また、簿記を取得していれば、定めた目標に対してコツコツ努力ができるという「計画性」や「実行力」、さらに「向上心」を持っているということもアピールできます。
このような点から、簿記は書類選考で有利に働く、あるいは最低限求められる可能性が高いです。
簿記の評価については、「簿記は2級から評価される?3級は評価されない?元面接官が語ります」も合わせてご確認ください。
3) 適性判断
「会計」という分野の適性が自分にあるのかどうかを見極めることで、経理に転職すべきか否かを判断することができます。
そして、「会計」に対する向き不向きを判断する方法として、簿記の受験はおすすめです。
簿記3級を受験してあまり苦がない、あるいは苦しいが割と楽に合格できた場合は会計に対する適性があるので、経理の道に進んでも問題ありません。
逆に全く面白さを感じず、結果も不合格だった場合はあまり適性がない可能性がありますので、他の道を検討した方がよいかもしれません。
4) 転職後の実務
最後の点は転職とは必ずしも関係しておりませんが、実務についた際に簿記を取得していると、始めからスムーズに業務をこなすことができます。
スタートダッシュを切って、同僚と比べて頭1つ抜けることは大切です。
始めに「仕事ができる」と思わせれば仕事が多く舞い込んできて、自身のスキルも上がりさらに多くの仕事が舞い込んでくるという、いい流れにのることができます。
反対に、この流れにのらないと、後から巻き返すのは非常に難しいです。
5) 注意点
簿記の知識はあくまでプラスαの要素であり、簿記を持っているから採用するといったことは基本的にありません。
そのため、過去の実務経験や実績などをしっかりとアピールする必要があります。
面接でしっかりとアピールしても景気の良し悪しや年齢などでうまくいかない場合も当然ありますので、その場合は縁がなかったくらいに思っておけばいいです。
4. 履歴書の書き方
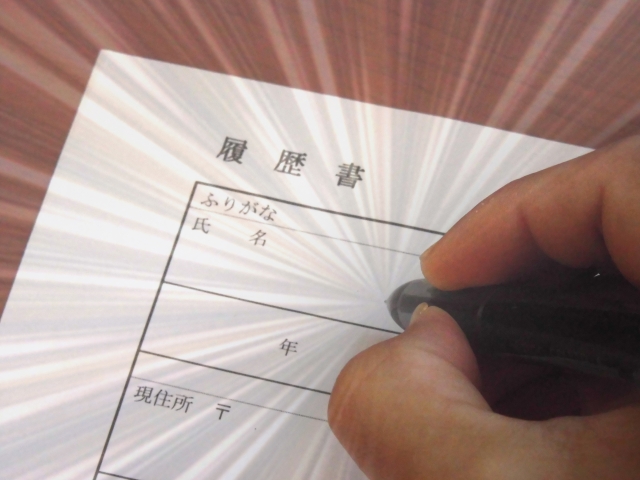
1) 正式名称を記載する必要がある?
日商簿記検定の正式名称は「日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験」となります。
それでは、履歴書に書く際は正式名称で書く必要があるのでしょうか?
履歴書には「日商簿記検定試験〇級」の記載で問題ありません。
本来履歴書の資格欄には正式名称を書く必要がありますが、日商簿記の場合は正式名称が長く、正式名称を知っている人も少ないため、正式名称を記載すると逆に紛らわしくなる可能性があります。
また、日商簿記検定という言葉は一般に認知されており、採用する側で知らない人はほとんどいません。
そのため、正式名称ではなく「日商簿記検定試験〇級」の記載の方が望ましいです。
2) いつの日付?
合格証に記載の日付を取得日として、履歴書に記載するのが望ましいです。
日商簿記の場合は、試験実施日が記載されております。
3) 3級から履歴書に書いて良い?
簿記2級であれば迷わず書くかもしれませんが、簿記3級のみ取得している人は、履歴書に書いても良いのか迷われるかもしれません。
結論としては、簿記3級から記載すべきです。
3級しか持っていないという理由でマイナス評価を受けることはなく、むしろ何も記載がない方がマイナス評価を受ける可能性が高いです。
また、3級を取得していることで、会計周りの最低限の知識はあることをアピールできます。
4) NGな書き方
1点注意していただきたいのは、単に「簿記検定〇級」と記載することです。
簿記には以下の3種類があり、単に簿記検定と記載するとどの簿記のことかわからないためです。
・「全経簿記」(公益社団法人全国経理教育協会)
・「全商簿記」(財団法人全国商業高等学校協会)
ベースにある考え方はどれも変わりませんが、難易度や目的などがそれぞれ異なるため、自身が取得したのが日商なのか全経なのか全商なのかの違いははっきり記載してください。
5. 終わりに

いかがでしたでしょうか?
転職やその後のキャリアを有利に進めるために、簿記が必要だということがお分かりいただけましたでしょうか。
簿記取得などの事前準備をしっかりして、履歴書や面接などの対策も行い、転職に臨みましょう。
6. まとめ
◆応募企業の選定や書類選考にも簿記の知識が役に立つ。
◆履歴書に書く際は単に「簿記検定」と書くのはNG。