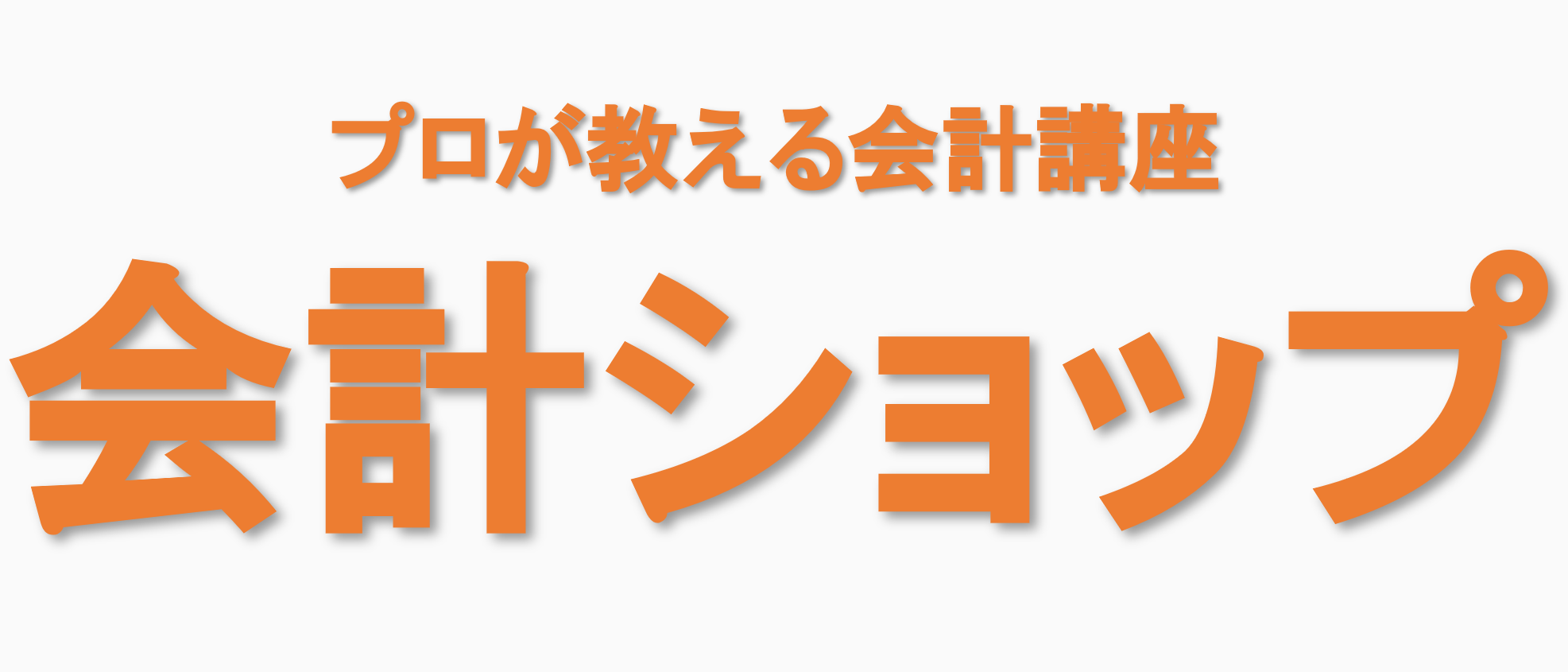簿記2級の勉強を始める際に多くの人が悩むのが、商業簿記と工業簿記はどっちを先に勉強すべきか?といった点です。
そこで今回は、まず商業簿記と工業簿記の違いについて解説した上で、商業簿記と工業簿記のどちらを先に勉強すべきかについて、お伝えしていきます。
また後半では、商業簿記と工業簿記それぞれの勉強のコツについても紹介しておりますので、ぜひご一読ください。
1. 簿商業簿記と工業簿記の違い
1) 商業簿記とは?
2) 工業簿記とは?
3) 商業簿記と工業簿記の違いは?
2. 商業・工業どっちから勉強する?
1) 簿記3級を勉強済みの場合
2) 簿記2級から勉強する場合
3. 商業簿記・工業簿記のコツ
1) 商業簿記の2つのコツ
2) 工業簿記の2つのコツ
4. 終わりに
5. まとめ
1. 商業簿記と工業簿記の違い

1) 商業簿記とは?
商業簿記とは、商品を売買する商業経営を対象とした簿記であり、小売業や卸売業など多くの業種が対象となります。
商業簿記のポイントとしては、以下が挙げられます。
・簿記検定3級は全て商業簿記
・製造業以外の多くの業種に当てはまる
・一般的な取引を扱うのが商業簿記
商業簿記の定義を覚えるよりも、後述する工業簿記以外は商業簿記と覚えてしまった方が、しっくりくるかと思います。
商業簿記で扱う具体的な分野については、以下の簿記3級と2級の、商業簿記部分の試験範囲を参考にしてみてください。
・現金預金
・売掛金と買掛金
・その他の債権と債務
・手形
・債権の譲渡
・引当金
・商品
・有形固定資産
・収益と費用
・税金
・各種決算整理手続
・資本金
・利益剰余金
・剰余金の配当
・有価証券
・債務の保証
・無形固定資産
・投資その他の資産
・リース取引
・外貨建取引
・税効果会計
・未決算
・資本剰余金
・本支店会計
・連結会計
2) 工業簿記とは?
工業簿記とは、製品を製造する工業経営を対象とした簿記であり、製造業が対象となります。
前述の商業簿記が「原価30円の商品を100円で売り上げる」といった一般的な取引を扱うのに対して、工業簿記は「原価30円をどうやって計算するのか?」といった内容を中心に扱います。
商業簿記の場合、原価30円は単純に30円で仕入れた商品を意味しますが、工業簿記の場合は自社で製造するため、材料を仕入れて機械や手作業で加工した結果として製品30円、つまりは原価30円が計算されます。
このように製品の原価を計算して(「原価計算」と言います。)、その過程・結果を簿記のルールに従って記帳していくのが、工業簿記となります。
…かかった費用を集計するだけだから、原価の計算って簡単なのでは?と思った人もいるかもしれません。
ただ、原価計算はそこまで単純なものではありません。
例えば自動車を製造する場合、主な原材料は以下となりますが、1台1台それぞれいくらで仕入れた材料が、何kg使用されているか把握することは困難です。
・アルミニウム
・プラスチック樹脂
・銅
また、各工程で関わる作業員の給料や、各工程で使用される機械の減価償却費・電気代なども、1台あたりいくらか計算する必要があります。
さらに、一定の割合で材料の不備や作業工程での失敗なども発生します。
そのため、工業簿記の原価計算は、ただ費用を集計するだけの簡単なものではなく、一定の仮定を置いて計算する複雑なものとなるのです。
3) 商業簿記と工業簿記の違いは?
それでは具体的に、商業簿記と工業簿記にはどのような違いがあるのでしょうか?
前述の点も含めて、順に解説していきます。
① 対象業種の違い
・商業簿記:多くの業種(製造業以外)
・工業簿記:製造業
② 勘定科目の違い
商業簿記と工業簿記で表現が異なる勘定科目
・商業簿記:商品
・工業簿記:製品
工業簿記特有の勘定科目
・材料
・労務費
・経費
・製造間接費
・仕掛品
・月次損益
③ 計算期間の違い
・商業簿記:1年
・工業簿記:1ヶ月
*商業簿記の場合、財務諸表という形式で外部に公表するのは1年ですが、内部の意思決定のために、工業簿記と同様に月次決算を行うのが通例となります。
④ 試験範囲の違い
・商業簿記:広くて浅い
・工業簿記:狭くて深い
2. 商業・工業どっちから勉強する?

ここでは、簿記2級を勉強するにあたり、商業簿記と工業簿記のどちらを先に勉強した方がいいのか?といった点について、以下の2つの場合に分けて解説していきます。
・簿記2級から勉強する場合
自分が該当する方の内容を、ぜひ参考にしてみてください。
1) 簿記3級を勉強済みの場合
簿記3級を勉強済みの場合、商業簿記と工業簿記のどちらを先に初めても問題ありません。
簿記3級で商業簿記を学習しているため、王道は商業簿記からですが、工業簿記の方がパズル感覚で頭に入りやすい人もいます。
いずれにしろ、どちらか始めに決めた方を、一定のところまでやり切ることが大切です。
少し手を出したところで苦手意識を感じて他方に変更した場合、後に苦手なものが残っているという感覚が残り、モチベーションが低下してしまうためです。
また、一定のところまで勉強を進めることで理解が深まるため、初期の段階で得意か苦手か判断するのは得策ではありません。
…とは言っても、何かしらの判断基準がほしい人もいるかと思います。
そこで、試験勉強における商業簿記と工業簿記の違いについて、以下に列挙しておきますので、参考にしてみてください。
【商業簿記の特徴】
・簿記3級の延長なので取りかかりやすい。
・最終的な勉強量は工業簿記よりも多い。
・工業簿記よりも『読解力』が要求される。
【工業簿記の特徴】
・初めて学習する内容なので理解しづらい。
・最終的な勉強量は商業簿記よりも少ない。
・商業簿記よりも『数字力』が要求される。
2) 簿記2級から勉強する場合
簿記2級から勉強する場合は、商業簿記から勉強するのがおすすめです。
工業簿記は商業簿記の基礎知識を前提としており、少なくとも簿記3級レベルの知識がつくまでは、商業簿記をやった方がいいと考えられるためです。
ただ、簿記2級の中から簿記3級に相当する部分だけをピックアップして学習するのは、非常に手間となります。
そのため、いきなり簿記2級を勉強するのではなく、まずは簿記3級から勉強することを検討してみてください。
(簿記2級から受験することのメリット・デメリットについては、「簿記2級からいきなり受験?受験資格はないので可能?」も合わせてご確認ください。)
簿記講座の元運営責任者が、「講座代金(安さ)」と「講座との相性(わかりやすさ)」の観点から、おすすめ通信講座を以下の5つに絞り、メリット・デメリットについて解説してみました。
・クレアール
・フォーサイト
・ネットスクール
・CPA会計学院
・スタディング
詳細は「簿記の通信講座おすすめ5選!安さとわかりやすさで比較すると..」をご確認ください。
3. 商業簿記・工業簿記のコツ

それでは最後に、商業簿記と工業簿記それぞれの、勉強のコツについて見ていきましょう。
1) 商業簿記の2つのコツ
① 仕訳の暗記を徹底する
商業簿記の1つ目のコツは、「仕訳の暗記を徹底する」ことです。
簿記2級の商業簿記では、リース取引・税効果会計・連結会計といった、難解な論点が追加されます。
また、簿記3級で扱った各論点もより深い内容となり、学ぶことが格段に増えるため、多くの受験生を悩ませます。
ただ、商業簿記の基本は仕訳であり、極論を言えば全て仕訳が切れれば、後は集計するだけとなります。
3級に比べて内容が難しくなったとはいえ、仕訳を全て暗記すれば問題は解けます。
ではどうやって暗記するのか?というと、何のひねりもないですが、ひたすら反復することです。
もちろん1つ1つの仕訳を理解することも大切ですが、「簿記はスポーツ」と言われるように、理屈抜きで「この場合はこの仕訳を切る」といった仕訳のルールを反復により丸暗記することが、実は商業簿記の実力をつける近道なのです。
「なぜそうなるのか?」ではなく、「そういうものなんだ」と受け入れて、丸暗記してみてください。
不思議なもので、丸暗記を繰り返していると、気付くと理解が進んでいることも多いです。
以上より、「仕訳の暗記を徹底する」ことは、商業簿記のコツと言えます。
② 満点ではなく合格点を狙う
商業簿記の2つ目のコツは、「満点ではなく合格点を狙う」ことです。
商業簿記は工業簿記と比べて範囲が広く、全範囲を隅から隅まで勉強するのは、現実的ではありません。
また近年では、簿記1級の商業簿記の一部の論点が、簿記2級の範囲となるケースがあり、簿記2級の商業簿記の試験範囲がさらに広がっております。
つまり、満点を目指して勉強すると、相当勉強時間に余裕がある人でない限り、途中で挫折するのが目に見えているのです。
さらに、現時点で4割解答できる人が7割(合格点)をとるために必要な勉強時間と、7割を10割(満点)に上げるために必要な勉強時間とでは、同じ3割アップでも後者の方が何倍も時間がかかり大変です。
にもかかわらず、満点をとろうが合格点をとろうが、対外的な評価は変わらないため、満点を目指すのは非常に費用対効果が悪い戦略と言えるのです。
以上より、「満点ではなく合格点を狙う」ことは、商業簿記のコツと言えます。
2) 工業簿記の2つのコツ
① 過去問を徹底的に利用する
工業簿記の1つ目のコツは、「過去問を徹底的に利用する」ことです。
工業簿記は商業簿記と比べて範囲が狭く、出題パターンが限られています。
そのため、過去問を徹底的に利用して出題パターンを押さえることが、効率的な勉強につながります。
この点、各予備校が出している予想問題でもいいのでは?と思われるかもしれません。
しかし、予想問題はあくまで過去問をもとに傾向を分析したものであり、出題パターンを把握する上で過去問以上の教材にはなりえません。
では何回分の過去問を解けばいいのか?というと、最低限9回分、つまりは3年分の過去問を解くことで、ある程度のパターンを押さえることができます。(可能なら15回分、つまりは5年分の過去問を解くことをおすすめします。)
また、過去問は少なくとも2回以上は解いてください。
ただし、満点だった回は再度解きなおす必要はありません。
以上より、「過去問を徹底的に利用する」ことは、工業簿記のコツと言えます。
② 満点を狙う
工業簿記の2つ目のコツは、「満点を狙う」ことです。
前述の通り工業簿記は出題パターンが限られているため、満点を狙うことも十分可能です。
工業簿記で満点の40点をとることができれば、商業簿記は60点満点の半分の30点をとれば合格点(70点)に届く計算となり、商業簿記の負担を格段に軽くすることができます。
それでは具体的に、満点をとるためには何を意識すればいいのでしょうか?
この点、広く浅く出題される商業簿記では仕訳を『暗記』することをおすすめしましたが、これとは反対に、狭く深く出題される工業簿記では各取引の内容を『理解』することに重点を置くのがポイントとなります。
なぜこの公式を使うのか?なぜこのような計算になるのか?といったことを常に考えることが、工業簿記のパターンを理解することにつながり、満点をとるための大きな一歩となるのです。
以上より、「満点を狙う」ことは、工業簿記のコツと言えます。
「理解する」のと「理解した気になる」の間には非常に大きな差があり、言うまでもなく合格するために必要なのは、理解することです。
そして、自分の理解度を測るためには、アウトプット、つまりは過去問などの問題演習が大切となります。
アウトプットに取り組むことで、自分が何を理解できていて、何を理解できていないのかがわかるため、積極的に過去問を利用しましょう。
4. 終わりに

商業簿記と工業簿記の違いや、どちらを先に勉強すべきか?といった点についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
商業簿記と工業簿記の特徴を押さえてしっかりと対策を練ることで、簿記2級の合格を勝ち取ってください。
5. まとめ
・商業経営を行う多くの業種で使用
・「商品」勘定を使用
・計算期間は1年
◆工業簿記
・工業経営を行う製造業などで使用
・「製品」勘定を使用
・計算期間は1ヶ月
・原価計算を行う
◆簿記3級勉強済み:どちらからでもOK
◆簿記2級から勉強:商業簿記から