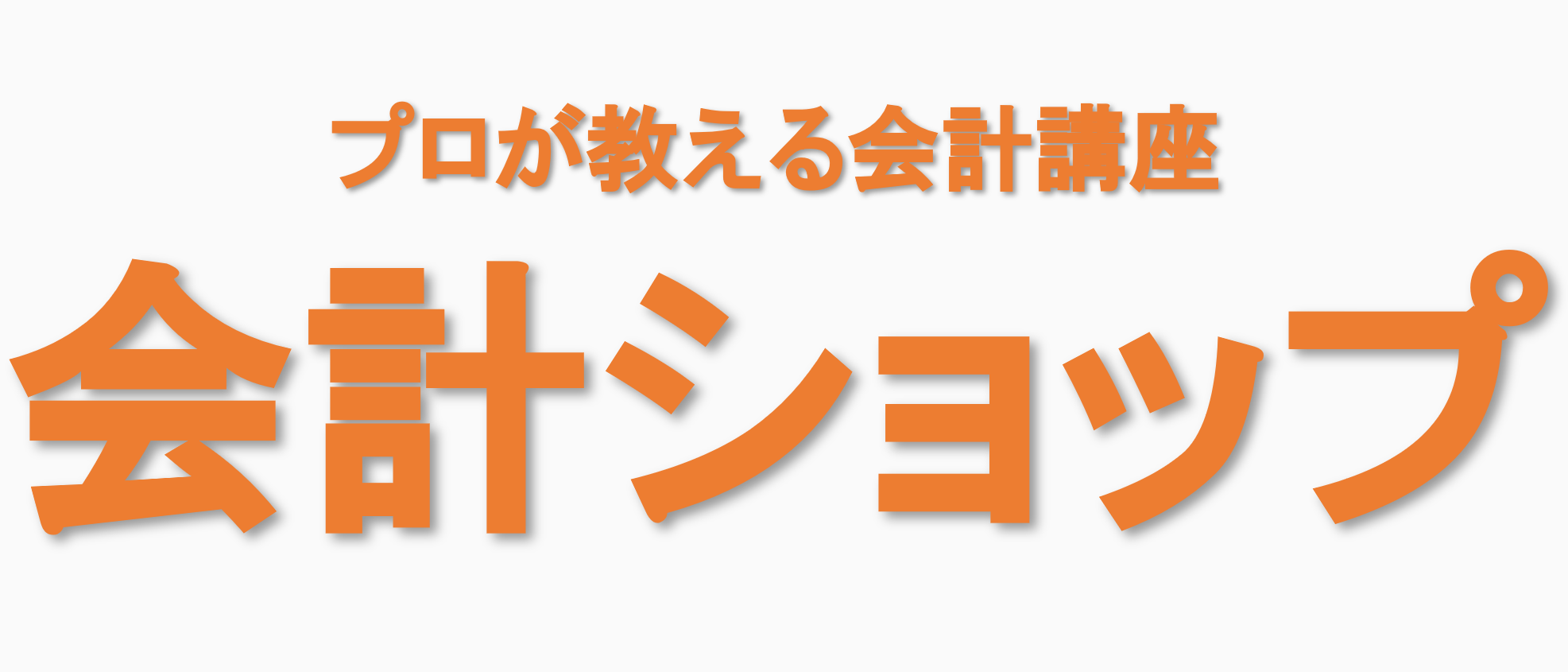中小企業やスタートアップ企業の人であれば、
経理部員を雇うか?
経理業務を税理士に任せるか?
といった内容で判断に迷ったことが、一度はあるのではないでしょうか?
確かに、税務面で税理士と顧問契約を結ぶのであれば、経理業務も一緒にお願いした方が、メリットが大きいとも言えます。
しかし、税理士に経理を任せることは、デメリットも大きく、避けた方がいいです。
経理は社内で行い、税務面について必要に応じて税理士に相談する、といった付き合い方が良いと考えられます。
そこで今回は、税理士に経理を任せない方がいい理由について、順に4つお伝えしていきます。
また、後半では、経理が税理士を利用する際に、押さえるべきポイントについても解説しておりますので、ぜひご一読ください。
(*本記事では、「外部の」税理士に経理業務を委託することのデメリットを述べており、税理士を経理として雇うこと、あるいは、経理部員が税理士資格を取得することとは異なりますので、ご留意ください。)
1. 税理士に経理を任せない方がいい理由
1) 事業数値を社内で把握できない
2) 税理士事務所を切り替えにくい
3) 税理士は経理の専門家ではない
4) 費用が高い
2. 経理が税理士を利用する際のポイント
1) 税理士への依頼内容は明確か
2) 社内の経理でできないか?
3) セキュリティ対策は?
4) お金だけ払っていないか?
5) 事業内容を理解しているか?
3. 終わりに
4. まとめ
1. 税理士に経理を任せない方がいい4つの理由
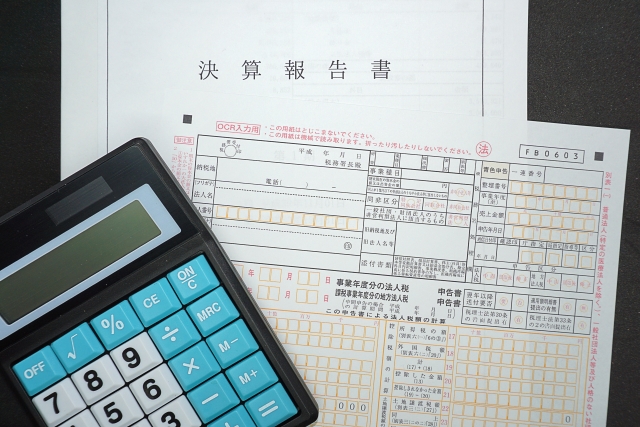
1) 事業数値を社内で把握できなくなる
税理士に経理を任せない方がいい1つ目の理由としては、「事業数値を社内で把握できなくなる」ことが考えられます。
営業やマーケティングなどの、各部署ごとに必要となる事業数値は、各部署が把握しています。
一方で、会社全体の事業数値、つまりは売上・費用・利益の金額や事業別の詳細などについては、経理が把握しています。
会社の経営戦略を立てる際に、まず現状を把握する必要があるのですが、税理士に経理を任せている場合、社内に誰も現状の数値を説明できる人間がいなくなってしまいます。
もちろん、税理士がまとめた決算資料を見れば、ある程度のことはわかりますが、その数字が出来上がった背景がわからず、今後の経営戦略策定に必要な、十分な議論が行えない可能性があります。
以上より、「事業数値を社内で把握できなくなる」ため、税理士に経理を任せない方がいいと言えます。
2) 税理士事務所を切り替えにくくなる
税理士に経理を任せない方がいい2つ目の理由としては、「税理士事務所を切り替えにくくなる」ことが考えられます。
税理士に経理業務を依頼する場合、基本的には税務面の顧問契約とセットで依頼することが想定されます。
この場合に、例えば依頼している税理士の税務面での能力に不満を感じても、経理をお願いしている関係上、関係を切りづらくなります。
また、反対に、経理業務に不満を感じて、他の税理士事務所に経理業務を依頼したい、あるいは経理部員を雇いたい場合でも。税務面の顧問契約がある関係上、関係を切りづらくなります。
以上より、「税理士事務所を切り替えにくくなる」ため、税理士に経理を任せない方がいいと言えます。
3) 税理士は経理の専門家ではない
税理士に経理を任せない方がいい3つ目の理由としては、「税理士は経理の専門家ではない」ことが考えられます。
税理士は税務の専門家ではありますが、経理の専門家という訳ではありません。
税務申告や節税対策などのアドバイスを行うのと、そのもととなる決算書類を作成するのとは、似て非なる業務です。
もちろん、経理が得意な税理士もいますが、反対に、税理士だからといって、必ずしも経理が得意であるわけではありません。
税理士資格を持っていなくても、経理としての経験をある程度積んだ人の方が、経理としては望ましいです。
以上より、「税理士は経理の専門家ではない」ため、税理士に経理を任せない方がいいと言えます。
4) 費用が高い
税理士に経理を任せない方がいい4つ目の理由としては、「費用が高い」ことが考えられます。
一概には言えませんが、税理士という専門家に経理業務を委託する場合は、それなりの費用がかかることが想定されます。
経理部員を雇うよりは、高い費用となりやすいです。
そして、税理士に払う費用は、文字通り単なる「費用」となります。
一方で、経理部員の給料を払う場合は、社内に経理ノウハウが蓄積していくため、将来に対する「投資」と捉えることができます。
税理士に対する費用は、投資とならず単なる費用となるため、相対的に高い費用となります。
以上より、「費用が高い」ため、税理士に経理を任せない方がいいと言えます。
2. 経理が税理士を利用する際のポイント5選

1) 税理士への依頼内容は明確か?
1つ目の経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントとしては、「依頼内容を明確にする」ことが挙げられます。
依頼内容が明確でないと、そもそも依頼金額の妥当性がわからず、依頼する側の経理も依頼される側の税理士も、「話と違う」といった事態を起こしかねません。
税理士への依頼内容としては、例えば以下のようなものが想定されます。
節税や必要な税務・会計処理などに関する定期的な相談。
・税務申告の代理、税務調査の立会い
納税者である会社の変わりに行う税務申告。
税務調査の対応。
・税務書類の作成
決算書や法人税・消費税などの確定申告書の作成。
・財務面のコンサルティング
資金繰りや融資の相談・助成金の申請など、財務面でのコンサルティング。
全ての業務を依頼する必要はなく、経理側で今税理士の力を必要としている業務を明確にして、その業務だけ依頼することで、お互いの認識の違いをなくすことができ、顧問税理士と良い関係を築くことができます。
以上より、「依頼内容を明確にする」ことは、経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントと言えます。
ベンチャー勤務時代は、社員数もまだ少なく経理部員も少なかったため、顧問税理士の力を借りていました。
決まった業務を依頼するのではなく、何かあったら相談するという包括契約のスタイルで、毎月固定額を支払っていました。
何も起こらなかった月は「もったいない費用だな。。」と思いつつ、いざ税務調査や買収などの案件で専門知識が必要となった際は、かなり助けられていました。
事業環境の変化が激しい会社では、今まだ顕在化していない税務問題についても後々対応する必要が出てくる可能性があるため、特定の業務ではなく包括的に税理士と契約するのも1つの方向性です。
2) 社内の経理でできないか?
2つ目の経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントとしては、「社内でできないか検討する」ことが挙げられます。
そもそも社内でできる業務を大した理由もなく税理士に依頼すると、後から必ず「何で依頼したの?」と言ってくる人が出ます。
そうならないためにも、依頼予定の業務について、「なぜ依頼するのか?」「社内の人員でできないか?」といった点は検討しておくべきです。
それなりに経験のある経理部員を採用して、社内でできることを増やしておくのも重要なことです。
外部リソースに頼りすぎると、社内にノウハウや知識が蓄積されず、経理部全体としてのスキルが磨かれない可能性もあります。
また、依頼される税理士からしても、より専門的な内容を依頼された方が、税理士としてのスキルも磨かれ市場価値も上がるため、社内でできることは極力社内でやった方が良いです。
(経理業務のアウトソーシングについては「経理をアウトソーシング・外注する際に注意すべき7つのこと」をご参照ください。)
以上より、「社内でできないかを検討する」ことは、経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントと言えます。
3) セキュリティ対策は?
3つ目の経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントとしては、「セキュリティ対策は問題ないか確認する」ことが挙げられます。
いずれの業務を税理士に依頼するにせよ、会社としてかなり機密性の高い情報を税理士に共有することとなります。
契約する際に税理士の能力や顧問料ばかり目が行き、セキュリティ対策については確認がおろそかになることが多いです。
セキュリティ面については、主に「事前」の予防と「事後」の対策に分けられます。
① 事前の予防策
情報が漏洩するのを「防ぐ」ための対策については、情報受け渡し時のパスワードなど基本的なものを除いて、外部の会社やソフトウェアを使ってセキュリティ対策しているか否かで判断するのも1つの方法です。
インターネットを通じたセキュリティに関する脅威は日進月歩で進化しており、それに対する対策とは常にイタチごっことなります。
そのため、個人で対策するには限界があるので、外部の会社やソフトウェアの利用の有無でセキュリティ状況を判断してみてください。
② 事後の対応策
当たり前のことですが、情報漏洩が発覚したら状況を速やかに把握して関係者に連絡すると共に、二次被害が発生しないように対策を講じる必要があります。
つまり、税理士側で情報漏洩が発生した際に、隠さずすぐに報告してくれるか否かというのは、セキュリティ面においてとても重要なこととなります。
、、、どうやって判断すればいいの?と思われたかもしれませんが、何も難しいことはありません。
「普段の報連相の早さ」で、問題が発生した際のだいたいの報告までのスピードは予想できますので、できるだけ早い対応をしてくれる税理士を選んだ方が良いです。
また、普段から「問題発生時には即連絡してくれ」という旨を伝え続けることも重要です。
以上より、「セキュリティ対策は問題ないか確認する」ことは、経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントと言えます。
4) お金だけ払っていないか?
4つ目の経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントとしては、「何もしていないのにお金だけ払っていないか確認する」ことが挙げられます。
昔からお世話になっている税理士との契約を続けている企業に多いのが、お付き合いで関係を継続していることです。
「昔お世話になったから。。」という義理人情もあるかもしれませんが、あくまでビジネスとして割り切る必要があります。
事業内容が安定してきたら、特異な税務上の論点が発生することも少なく、昔の契約内容のままでは普段の依頼内容と比べて、過大に顧問料を支払っている可能性があります。
であれば、一度顧問税理士と腹を割って話して、それでも業務量に見合う顧問料にならなければ、他の税理士の利用を検討してみてください。
以上より、「何もしていないのにお金だけ払っていないか確認する 」ことは、経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントと言えます。
5) 事業内容を理解しているか?

5つ目の経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントとしては、「税理士は事業内容を理解しているか確認する」ことが挙げられます。
税理士は複数の会社と顧問契約を結んで収益を得ている関係上、一社一社の事業内容をあまり細かく把握していると、時間がかかりすぎて費用対効果が合わないと考える人もいます。
ただ、仕事を依頼する経理側からすれば、自社の事業内容をあまり理解せずに通り一遍の税務対応で終わられては困ります。
また、本来税理士側からしてみても、一社一社の事業内容を深く理解した方が、長期的な関係を築けて、かつ、一つ一つの税務相談に対する対応も短く終わらせることができるので、メリットが大きいです。
今契約している税理士が自社の事業についてあまり詳しくない、あるいは学ぶ気がないと感じたら、他の税理士を検討してみるのも1つの方法です。
以上より、「税理士は事業内容を理解しているか確認する」ことは、経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントと言えます。
3. 終わりに

経理が税理士を利用する際に押さえるべきポイントについてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
経理として譲れない点を明確にしながら、税理士と良好な関係を築くことで、経理業務の質とスピードを上げていきましょう。
4. まとめ
◆税理士事務所の切り替えが難しくなる。
◆税理士は税務の専門家であり、経理の専門家ではない。
◆費用が高い。