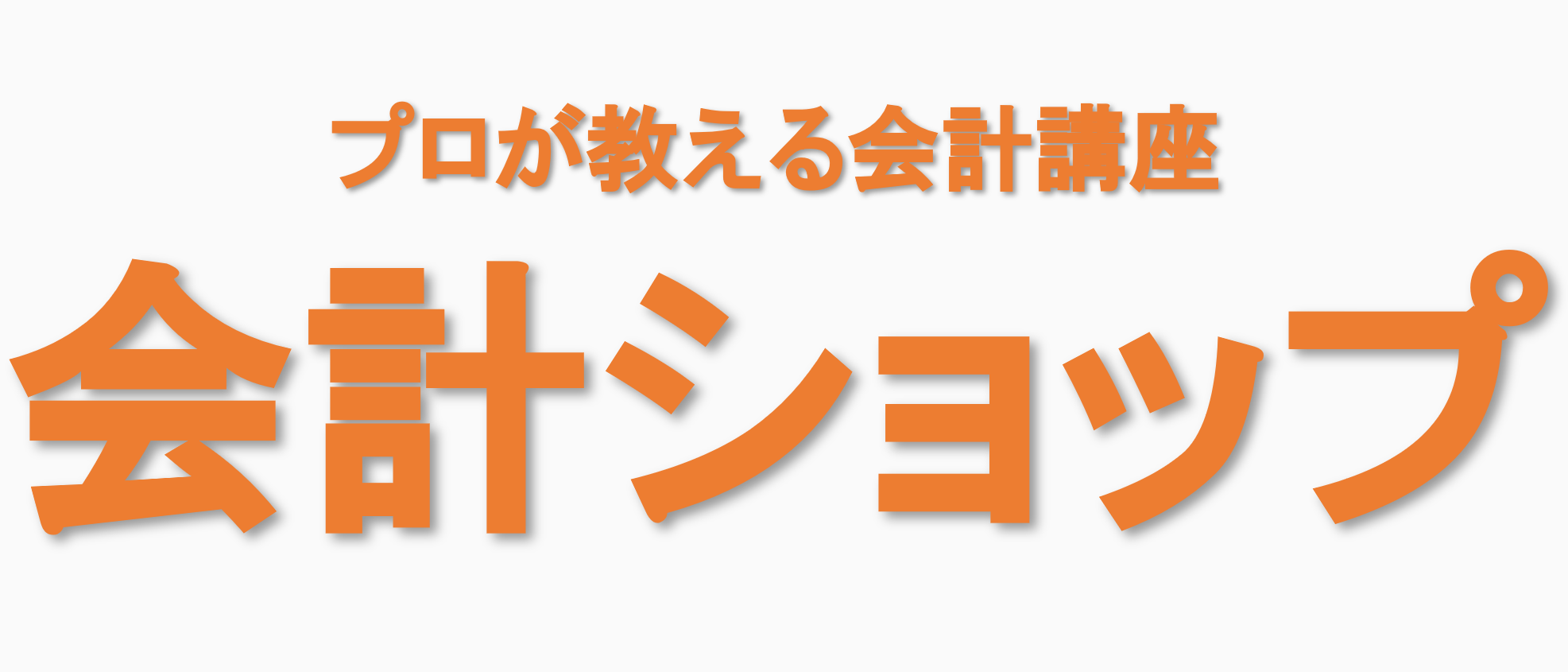資格としては簿記検定の方が有名であり、まだそこまで知名度は高くありませんが、近年じわじわと注目を集めている、ビジネス会計検定。
本記事では、最初のステップとなるビジネス会計検定3級の受験要項や難易度、受験のメリット・デメリットについて、順に解説していきます。
また冒頭では、ビジネス会計検定3級の勉強が必要か否かを判断する基準についてもお伝えしております。
ビジネス会計検定講座の講師である筆者の経験に基づいて解説しておりますので、ぜひご一読ください。
1. ビジネス会計検定3級が必要ない人
2. ビジネス会計検定とは?
3. 出題内容・形式と受験要項
4. 難易度は高い?低い?
5. 受験のメリット・デメリット
6. 勉強方法・勉強時間
7. 3級の評判・評価は?
8. 3級合格後の選択肢
9. 終わりに
10. まとめ
1. ビジネス会計検定3級が必要ない人

そもそも論ですが、ある程度会計に関する知識を持っている人の中には、
「3級は自分に必要ないのでは?」
と思っている方も、多いかと思います。
例えば、以下のような人達が想定されます。
・簿記3級合格者
・経理の経験者
・大学で会計を学んだ人
・株式投資で決算書を読んでいる人
ただ、決算書の分析スキルを学ぶビジネス会計検定3級は、単なる会計知識とは異なりますので、3級の勉強が必要か否かは慎重に判断する必要があります。
1つの判断基準として、以下の問題に即答できるのであれば、3級の勉強を飛ばして2級の勉強をする、あるいは、ビジネス会計検定を勉強しないという選択肢でも、問題ないかと思います。
① 安全性分析

② 収益性分析

③ 成長性分析

④ キャッシュ・フロー分析

⑤ 1株当たり分析

いかがでしょうか?
上記はビジネス会計検定3級で出題される5つの財務諸表分析の手法から、それぞれ代表的な問題を抽出したものです。
上記に即答できる人は、3級を受験する必要はなく、また、本記事もここで読み終えて問題ありません。
反対に、上記の内容が「さっぱりわからない」あるいは「曖昧な部分が多い…」と感じた人は、ビジネス会計検定3級を受験することをおすすめします。
それでは、ビジネス会計検定3級の概要について、見ていきましょう。
(参考:先ほどの答え)
① 安全性分析:自己資本比率

② 収益性分析:ROEの分解

③ 成長性分析:売上高の伸び率

④ キャッシュ・フロー分析:循環パターン

⑤ 1株当たり分析:PERによる割高・割安

2. ビジネス会計検定とは?

ビジネス会計検定は比較的新しく、まだ知名度がさほど高くない資格です。
まずは、ビジネス会計検定試験はどんな試験なのか、一緒に見ていきましょう。
既にビジネス会計検定についてご存知の方は、次の項目「3. 3級の出題内容・形式と受験要項」へお進みください。
1) ビジネス会計検定とは?
ビジネス会計検定を主催する大阪商工会議所の公式HPでは、ビジネス会計検定について以下のように説明されています。
財務諸表に関する知識や分析力を問うもので、財務諸表が表す数値を理解し、ビジネスに役立てていくことに重点を置いています。
財務諸表とは、いわゆる「決算書」。
損益計算書やキャッシュフロー計画書など、ビジネスパーソンなら一度は聞いたことのある書類で構成されています。
企業は、利害関係者に向けて情報開示をするために、財務諸表を作成します。
公式HPの説明を言い換えると、受験者はビジネス会計検定試験において、財務諸表を読み、企業の財務状況や経営成績等を分析する能力を問われることになります。
2) 財務諸表を読み解くことの大切さ
財務諸表とは、企業経営の健康診断書。
これを適切に読み解くスキルを持つことで、その企業に将来性はあるのか、経営リスクはどこにあるのか、経営陣の関心がどこにあるのか等、様々なことを数字を通して知ることができます。
ビジネスシーンでは、こういった能力を持つことは大きなアドバンテージとなるのです。
3) なぜビジネス会計検定なのか?
財務諸表の知識をつけることの有効性は、わかるかと思います。
一方で、会計知識の検定なら、簿記検定の方が有名なことも明らかです。
では、なぜ今ビジネス会計検定が注目されているのでしょうか?
その理由は、ビジネス会計検定と簿記検定の間にある、以下の決定的な違いにあります。
経理部門に所属しないビジネスパーソンや、企業に属さない学生、投資をする方にとって、より身近なスキルはどちらでしょうか?
それは後者、財務諸表を「読む」スキルですね。
ビジネス会計検定とは、多数の方々にとって、より実用的なスキルをダイレクトに学ぶことができる検定なのです。
ビジネス会計検定3級と簿記検定3級は、似て非なる試験です。
両検定には、以下のような共通点・相違点があります。
【共通点】
・会計の基礎知識が身に付く。
・受験資格の制限がない。
・1級は格段にレベルが上がる。
・2級までの取得で通常は問題ない。
【相違点】
| ビジ会3級 | 簿記3級 | |
| 決算書 | 分析 スキル |
作成 スキル |
| 申込者 (年間) |
1万人 | 30万人 |
| 合格率 | 70% | 40% |
| 主催 | 大阪商工 会議所 |
日本商工 会議所 |
| 回数 (年間) |
2回 | 3回 *ネット試験 は随時開催 |
| 試験 形式 |
マーク式 | 記述式 |
3. 出題内容・形式と受験要項

ビジネス会計検定には、1級から3級まで、3つのレベルが存在します。
既にある程度の知識をお持ちの方なら、いきなり2級や1級から挑戦することも可能です。
1級と2級、2級と3級など、隣り合う2つの級を併願することも可能です。
ここでは、最もチャレンジしやすい3級について、ご紹介します。
1) 3級の出題形式と試験時間
ビジネス会計検定3級の回答は、全問マークシート方式で行います。
全50問(各2点)の100点満点のうち、70点以上で合格となります。
試験時間は2時間、これとは別に当日行われる説明や配布・回収に15~30分程度かかります。
(*その分試験時間が減るわけではなく、各会場ごとに説明・配布が終わった時点から2時間がカウントされますので、ご安心ください。)
問題には正誤の判断や、言葉や数字の選択問題、電卓を使った計算問題などがあり、前半(大問Ⅰ,Ⅱ)ではそれぞれが独立した問題である「個別問題」が、後半(大問Ⅲ,Ⅳ)では与えられた財務諸表に関連する基礎的な分析を行う「総合問題」が出題されます。
例えば、第28回~第36回の試験では、以下のような問題構成や出題内容となっております。
(問題構成)
| 大問 | 28回 | 29回 | 30回 |
| Ⅰ | 12問 | 9問 | 12問 |
| Ⅱ | 10問 | 15問 | 13問 |
| Ⅲ | 13問 | 13問 | 12問 |
| Ⅳ | 15問 | 13問 | 13問 |
| 大問 | 31回 | 32回 | 33回 |
| Ⅰ | 14問 | 12問 | 13問 |
| Ⅱ | 13問 | 13問 | 14問 |
| Ⅲ | 13問 | 11問 | 12問 |
| Ⅳ | 10問 | 14問 | 11問 |
| 大問 | 34回 | 35回 | 36回 |
| Ⅰ | 12問 | 13問 | 12問 |
| Ⅱ | 14問 | 13問 | 13問 |
| Ⅲ | 13問 | 24問 | 25問 |
| Ⅳ | 11問 | – | – |
(出題内容)
第28回試験(2021年3月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全12問)】出題内容はこちら
・金融商品取引法の適用範囲、目的・貸倒引当金
・減価償却費
・のれん
・繰延資産
・自己株式、新株予約権
・損益計算書
・発生主義、費用収益対応の原則
・営業利益、営業外費用
・税効果会計
・投資/財務活動によるキャッシュフロー
・1株当たり分析(BPS)
出題内容はこちら
・会社法上の計算書類に含まれるもの・総額主義の原則
・流動負債
・販管費、営業外費用、特別損失の分類
・営業活動によるキャッシュフロー:間接法
・定量情報と定性情報
・当期製品製造原価の計算
・営業外収益の計算
・CF計算書の現金及び現金同等物
出題内容はこちら
・収益/費用とキャッシュイン/アウトフロー・キャッシュフロー循環
・貸借対照表構成比率分析
・損益計算書構成比率分析
・収益性分析(営業利益率/原価率)
・安全性分析(流動比率/正味運転資本)
・フリー・キャッシュフロー
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(ROEの分解)
・収益性分析(総資本回転率)
・収益性分析(財務レバレッジ)
・1株当たり分析(PBR)
・1株当たり分析(時価総額)
・生産性分析(労働効率と労働時間/1人当たり売上高)
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・営業活動によるキャッシュフロー:間接法
・キャッシュフロー循環
・成長性分析(売上債権)
・成長性分析(売上総利益、売上高)
・安全性分析(目的、流動比率)
・安全性分析(手元流動性)
・安全性分析(自己資本比率)
・収益性分析(総資本経常利益率の分解)
・1株当たり分析(EPS)
・1株当たり分析(PER/BPS)
第29回試験(2021年10月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全9問)】出題内容はこちら
・金融商品取引法の開示、適用範囲・貸借対照表、流動固定分類
・売上総利益
・固定資産
・販売費及び一般管理費
・税効果会計
・現金及び現金同等物
・当座比率、財務レバレッジ
・総資本回転率
出題内容はこちら
・金商法の開示書類・前渡金(流動資産)
・有価証券(流動資産)
・有形固定資産に該当するもの
・投資その他の資産に該当するもの
・貸借対照表での表示区分
・発生主義の原則
・社債利息
・CF計算書、間接法
・投資活動によるCFに該当するもの
・キャッシュフロー循環
・マイナスの値になることがあるもの
・営業利益、税引前当期純利益の計算
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・売上高売上原価率
・当期純利益の伸び率
・当座比率
・フリー・キャッシュフロー
・収益性分析(総資本経常利益率、自己資本当期純利益率)
・収益性分析(総資本経常利益率の分解)
・1株当たり分析(PBR)
・生産性分析(1人当たり売上高)
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・棚卸資産の計算
・安全性分析(正味運転資本、流動比率)
・安全性分析(自己資本比率)
・成長性分析(対前年度比率、伸び率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・収益性分析(総資本回転率)
・1株当たり分析(PER)
第30回試験(2022年3月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全12問)】出題内容はこちら
・会社法の適用範囲、目的・事業用資産、金融資産の評価
・資本金への組み入れ、自己株式
・固定資産の減価償却
・純資産の部の区分け
・総額主義、実現主義、発生主義
・売上原価、売上総利益(粗利益)
・PLとCF計算書、CF計算書の役割
・間接法によるCF計算書
・営業外損益
・従業員1人当たり売上高
・売上高、売上原価の伸び率の計算
出題内容はこちら
・金商法の開示書類・BSの勘定式と報告式
・総額主義、売掛金と貸倒引当金の表示
・損益計算書
・固定資産の減損損失
・キャッシュフロー循環
・1株当たり当期純利益
・無形固定資産の集計
・固定負債の集計
・現金及び現金同等物の集計
・財務活動によるCFの集計
・当期商品仕入高の計算
・営業利益の計算
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・総資産、売上高の伸び率
・安全性分析(流動比率)
・安全性分析(手元流動性)
・売上高販売費及び一般管理費率
・売上原価率
・収益性分析(営業利益率)
・フリー・キャッシュフロー
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率の分解)
・生産性分析(1人当たり売上高)
出題内容はこちら
・貸借対照表構成比率・投資その他の資産
・成長性分析(売上高の伸び率)
・安全性分析(正味運転資本)
・安全性分析(当座資産)
・安全性分析(自己資本比率)
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・収益性分析(経常利益率、当期純利益率)
・収益性分析(総資本回転率)
・収益性分析(財務レバレッジ)
・1株当たり分析(PER)
・1株当たり分析(PBR)
・時価総額
第31回試験(2022年10月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全14問)】出題内容はこちら
・ディスクロージャー、財務諸表の範囲・貸借対照表の定義、負債(他人資本)
・貸借対照表の配列方法
・取得原価
・貸倒引当金
・流動資産、有価証券の区分
・のれん、創立費
・自己株式、新株予約権
・費用の計上基準、個別的対応と期間的対応
・税効果会計
・キャッシュ・フロー計算書
・手元流動性
出題内容はこちら
・会社法の適用範囲、目的・前渡金
・有形固定資産に該当するものの個数
・流動負債に該当するものの組み合わせ
・減価償却費、社債利息、販管費に該当するもの
・経常利益、当期純利益の計算
・営業活動によるCF(間接法)
・投資活動によるCFに該当するもの
・キャッシュフロー循環
・流動比率と正味運転資本
・自己資本利益率の分解
出題内容はこちら
・営業活動によるCFの計算・安全性分析(手元流動性)
・貸借対照表構成比率
・成長性分析(対前年度比率、伸び率)
・減収増益の判断
・安全性分析(当座資産、当座比率)
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・1株当たり分析(EPS)
・1株当たり分析(PER)
・1株当たり分析(BPS)
・1株当たり分析(PBR)
出題内容はこちら
・貸借対照表構成比率・収益性分析(売上総利益率、営業利益率)
・安全性分析(流動比率、当座比率)
・安全性分析(自己資本比率)
・フリー・キャッシュフロー
・安全性分析(正味運転資本)
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・収益性分析(総資本回転率、財務レバレッジ)
・時価総額
・生産性分析(1人当たり売上高)
第32回試験(2023年3月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全12問)】出題内容はこちら
・金融商品取引法の適用範囲、目的・流動固定分類
・重要性の原則
・減価償却の対象、定率法
・株主資本の構成(払込資本、留保利益)
・資本金、資本準備金への組み入れ
・その他有価証券評価差額金
・損益計算書の定義、実現主義
・売上高、粗利益の定義
・販売費及び一般管理費に含まれるもの
・特別利益に含まれるもの
・現金及び現金同等物
・営業CFの直接法と間接法
・収益性分析(総資本回転率)
出題内容はこちら
・計算書類に含まれるもの・報告式の貸借対照表
・有価証券の分類
・無形固定資産の金額の計算
・流動負債に含まれるもの
・売上高、営業利益の計算
・社債利息
・キャッシュフロー計算書について
・財務CFの金額の計算
・営業、投資、財務CFから会社状況を判断
・財務レバレッジと自己資本比率、ROEの関係
・1株当たり純資産=最低株価の目安
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・売上債権と仕入債務
・売上高売上原価率、粗利率
・安全性分析(手元流動性)
・安全性分析(自己資本比率)
・収益性分析(総資本回転率)
・収益性分析(売上高当期純利益率)
・1株当たり分析(EPS、PER)
出題内容はこちら
・流動負債の貸借対照表構成比率・売上高売上原価率、販管費率
・成長性分析(対前年度比率、伸び率)
・増収増益の判断
・安全性分析(流動比率、正味運転資本)
・安全性分析(当座比率)
・フリー・キャッシュフロー
・営業、投資、財務CFから会社状況を判断
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(総資本回転率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・収益性分析(売上高当期純利益率)
・1株当たり分析(PER)
・1株当たり分析(PBR)
・時価総額
・生産性分析(1人当たり売上高)
第33回試験(2023年10月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全13問)】出題内容はこちら
・会社法の目的、計算書類に含まれるもの・勘定式の貸借対照表の表示方法
・他人資本
・流動性配列法
・重要性の原則
・事業用資産の評価方法、時価の欠点
・棚卸資産の範囲
・貸付金の長短分類
・自己株式の定義、新株予約権の区分
・損益計算書の定義
・収益と費用の対応(期間的対応)
・総額主義の原則
・収益の計上基準
・営業外損益
・当期純利益、法人税等調整額
・キャッシュフロー計算書の定義、役割
・営業活動によるキャッシュ・フロー
・手元流動性
出題内容はこちら
・総額主義の原則・投資その他の資産に含まれるもの
・貸借対照表の項目と表示区分
・営業利益、売上総利益
・販売費及び一般管理費に含まれるもの
・税効果会計の適用により計上されるもの
・営業、投資、財務CFから会社状況を判断
・1株当たり純利益
・有形固定資産の計算
・営業外費用、経常利益の計算
・現金及び現金同等物の集計
・投資活動によるCFの計算
・配当性向
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・売上債権と棚卸資産
・安全性分析(手元流動性)
・安全性分析(正味運転資本)
・収益性分析(売上高経常利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・収益性分析(総資本経常利益率)
・他人資本の計算
・安全性分析(自己資本比率)
・1株当たり分析(BPS)
・1株当たり分析(PBR)
・1株当たり分析(PER)
・収益性分析(財務レバレッジ)
・収益性分析(総資本回転率)
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・売上高売上原価率、営業利益率
・収益性分析(総資本経常利益率)
・総資産からみた投資規模
・安全性分析(流動比率)
・安全性分析(当座比率)
・フリー・キャッシュフロー
・収益性分析(総資本営業利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・時価総額
・1株当たり分析(EPS)
・生産性分析(1人当たり売上高)
・有形固定資産の貸借対照表構成比率
第34回試験(2024年3月実施)
【大問Ⅰ:個別問題(全12問)】出題内容はこちら
・ディスクロージャー、金商法の目的・貸借対照表の定義、勘定式の表示方法
・流動性配列法、総額主義の原則
・貸倒れの定義、貸倒引当金の表示場所
・減価償却の対象、定率法
・繰延資産の表示場所、開業費
・その他有価証券の分類、評価差額金の計上場所
・営業利益の定義、当期純損失との関係
・法人税等の定義、繰延税金資産・負債の計上場所
・キャッシュフロー計算書の役割
・現金及び現金同等物と現金及び預金の関係
・売上高の伸び率、売上原価率
・流動比率と当座比率の関係
・財務レバレッジと自己資本比率の関係
出題内容はこちら
・計算書類と財務諸表に含まれるもの・事業用資産の評価と取得原価の長所
・売買目的有価証券の区分
・無形固定資産に含まれるもの
・流動負債の合計額の計算
・株主資本の金額の計算
・減価償却費と有価証券売却損の定義
・営業外費用に含まれるもの
・営業外収益の計算
・税引前当期純利益の計算
・キャッシュの範囲
・キャッシュフロー計算書の直接法と間接法
・財務活動によるCFに含まれるもの
・正味運転資本
出題内容はこちら
・財務諸表の穴埋め・安全性分析(手元流動性)
・安全性分析(当座比率)
・安全性分析(正味運転資本)
・安全性分析(流動比率)
・フリー・キャッシュフロー
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・1株当たり分析(EPS)
・1株当たり分析(BPS)
・1株当たり分析(PBR)
・収益性分析(財務レバレッジ)
出題内容はこちら
・負債の貸借対照表構成比率・成長性分析(対前年度比率、伸び率)
・売上原価率、粗利益率
・売上総利益率、営業利益率、販管費率
・営業、投資、財務CFから会社状況を判断
・安全性分析(自己資本比率)
・収益性分析(総資本経常利益率)
・収益性分析(自己資本当期純利益率)
・時価総額
・1株当たり分析(PER)
・生産性分析(1人当たり売上高)
2) 3級の受験要項
①試験日・申込みスケジュール
3級の試験は、年2回、3月と10月に実施されます。
申し込み受付は、試験日の2〜3ヶ月前に始まり、1ヶ月ほどの期間を経て、受付終了となります。
直近の試験日程については、以下をご参照ください。
| 37回 | 38回 | |
| 試験日 | 2025 10/19(日) |
2026 3/8(日) |
| 申込期間 | 8/22(金) ~9/11(木) |
1/9(金) ~1/29(木) |
通常、試験日の2週間ほど前に、受験票が届きます。
結果は、成績表の発送によって試験日から1ヶ月強で知らされます。
②受験地
受験地は、全国から選ぶことができます。
札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡の中から受験地を選択できます。
③受験料の金額と支払い方法
3級は、受験料の金額においても、ビジネス会計検定の中で最も受験しやすい級となります。
4,950円(税込)を、インターネット・コンビニ・郵便振替のいずれかの方法で支払います。
④受験資格
学歴や性別、年齢・国籍を問わず、どなたでも受験可能です。
3) 問われる内容
3級の出題範囲は公式テキストに準拠したものとなりますため、以下の公式テキストの内容をしっかり押さえておく必要があります。
.jpg)
公式テキスト3級 第5版
具体的には、以下の内容となります。
◆第1章から第4章:財務諸表に対する「知識」を問う内容
・貸借対照表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書
◆第5章:財務諸表の「分析力」を問う内容
・成長性分析
・安全性分析
・収益性分析
・キャッシュフロー分析
・1株(1人)当たり分析
勉強を開始する前にまず、上記の全体像を押さえておきましょう。
目次を見て全体像を確認した上で勉強に取り組まないと、今自分がどこの勉強をしているかわからなくなり、迷子になってしまいます。
その結果、モチベーションが低下して、勉強をやめてしまう人も少なくありません。
また、目次を見る以外に全体像を把握する方法として、まず過去問を「見る」こともおすすめの方法となります。
初めに過去問を見ることで、問題を解くことはできなくても、何となく「こんな問題がでるんだな」というイメージが湧き、目次を見る以上に全体像を掴むことができます。
ビジネス会計検定3級であれば、公式の問題集に掲載されている過去問に、まずは目を通してみてください。
4. 難易度は高い?低い?

ビジネス会計検定3級では、財務諸表を分析し、理解するための基礎的な力を測ります。
会計初心者にも挑戦しやすいレベルのため、難易度は決して高くありません。
例えば、ここ数年の合格率は、以下の通りとなっております。
| 試験回数 | 受検者数 | 合格率 |
| 36回 | 3,810 | 51% |
| 35回 | 3,862 | 57% |
| 34回 | 3,361 | 71% |
| 33回 | 3,459 | 70% |
| 32回 | 3,495 | 62% |
| 31回 | 3,793 | 67% |
| 30回 | 3,484 | 64% |
| 29回 | 4,160 | 69% |
| 28回 | 4,321 | 68% |
| 27回 | 3,937 | 71% |
| 26回 | 2,886 | 63% |
| 25回 | 4,502 | 59% |
| 24回 | 3,859 | 62% |
| 23回 | 3,847 | 62% |
| 22回 | 3,438 | 59% |
年度によりばらつきのある合格率も、ここ数年では70%前後をキープしています。
受験者数が最も多いのも、3級です。
そのため、履歴書でのアピール力はさほど大きくありませんが、3級で基礎力をつけることで、次の級に必要な知識の土台を築くことができます。
しかし、最も基礎的な級とはいえ、あまりゆったりと構えていると、痛い目に合います。
受験料を無駄にしないためにも、しっかり対策を練って勉強しましょう。
短期間でビジネス会計検定に合格したいなら、会計ショップのビジネス会計検定講座がおすすめです。
頻出論点を短時間で講義するので、効率的に合格を目指すことができます。
・3級講義時間:約15分×20回
・2級講義時間:約20分×20回
・確認テスト、予想問題つき
5. 受験のメリット・デメリット
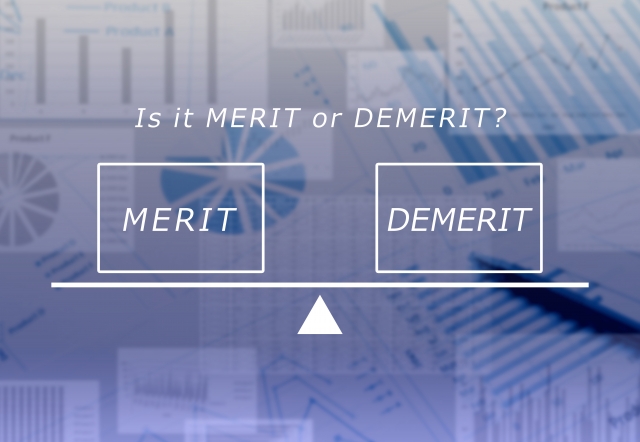
ここでは、3級を受験するメリットとデメリットについて、箇条書きで紹介していきます。
メリット
・企業分析や株式投資に役立つ
・2級のステップアップとなる
・簿記3級と相性がいい
・手頃な難易度で成功体験を積める
デメリット
・基礎を理解している人には退屈
・基礎だけではできることが少ない
ビジネス会計検定3級の知識だけでは、実務に応用できる範囲は限られるので、最終的には2級までの取得をおすすめいたします。
6. 勉強方法・勉強時間

ビジネス会計検定の勉強法は、公式テキスト・過去問題集を使用した独学が王道です。
合格率が70%の3級の難易度から考えても、公式テキストと公式問題集をしっかりとやり抜けば、合格は十分可能と言えます。
一方で、合格の可能性を上げるためには、ぜひ予備校の対策講座の利用も検討してみましょう。
専門の講師から教わり、最短距離で合格すれば、元は十分とれるかと思います。
合格するまでの勉強時間は、会計初心者の方で100時間を目安に考えておくと良いでしょう。
受験する試験日を決める際の、参考にしてください。
7. 3級の評判・評価は?

ここでは、ビジネス会計検定3級の評判・評価について、実際に勉強している人達の声をまとめてみました。
1) ビジネスパーソンの基礎教養
おまたせ☕️🍞🥚
— 🌿すかお@投資🌿 (@sukao_Asset) June 10, 2023
ビジネス会計少しずつ勉強してるけど財務諸表の基本が学べてためになるなー📘無論投資にも役立つしビジネスマンなら基礎教養として必要なレベルだと思う🤔この手の知識は今後ニーズ高まりそうだな!詐欺商材より絶対こっちの方が有益だわ👍 pic.twitter.com/VL7e8u908Z
財務諸表の基礎知識や株式投資に役立つ指標を学ぶことができるため、ビジネスパーソンにとっての基礎教養を学べます。
最低限の会計知識は今後一層ニーズが高まるので、ビジネス会計検定3級を勉強しておいて損はないです。
2) 3級はあくまで基本的な内容
ビジネス会計検定3級、公式テキストをとりあえず読み終えた
— FX_Wanko (@Asb8EVp9mrtnt2k) May 30, 2023
ちゃんとした分析は2級からかな?
3級はとりあえず基本的な語句を覚えるって感じやった
3級で学ぶ内容はあくまで、財務諸表や株式投資指標の基礎です。
そのため、応用力を身につけるためには2級までの勉強が必要、という意見もあります。
3) 中小企業診断士の勉強に役立つ
簿記3級+ビジネス会計3級を先に学習したおかげで、財務会計の学習がスムーズです。
— TY@中小企業診断士受験生 (@shindanshi_ty) June 19, 2023
原価計算は去年勉強したけど、ほとんど忘れていました。
気分的には経済学よりだいぶ楽です。
中小企業診断士の重要科目である「財務・会計」の関連資格として、ビジネス会計検定はよく名前が挙がります。
中小企業診断士の参考書だけだとつまずく人も多いので、まずはビジネス会計検定や簿記検定を勉強してみるのもおすすめです。
4) 経理以外なら簿記よりおすすめ
ビジネス会計、簿記に比べると認知低いし就職にも役に立たないと言われてるけど、簿記はどちらかと言うと経理や財務など実務で使う人にはかなり有効だけど、それ以外のビジネスマンは作る過程よりも財務諸表読める方がよっぽど大事だと思うからビジネス会計学んだ方がいいんじゃないのかな?って思う。
— みう (@miu_ra_15) October 15, 2023
経理や財務以外の職種なら、簿記検定よりもビジネス会計検定の方が良いのでは?という意見も多いです。
一概にどちらが大切とは言えませんが、財務諸表の作成ではなく分析を目的とするのであれば、ビジネス会計検定をメインに勉強しても良いかもしれません。
8. 3級合格後の選択肢

ビジネス会計検定3級に合格した後の選択肢としては、どのようなものがあるのでしょうか?
まだ3級の勉強を始めていない段階でも、事前にしっかりと先を見据えておくことは、大切なことです。
そこでここでは、3級合格後の選択肢として、2つおすすめを紹介していきます。
1) ビジネス会計検定2級に進む
1つ目の3級合格後の選択肢としては、「ビジネス会計検定2級に進む」ことが考えられます。
王道の選択肢ではありますが、やはり3級合格後は、2級を目指すのがおすすめです。
2級を目指すべき主な理由としては、以下が挙げられます。
・扱う分析指標の数が増える
・合格率が40%と手ごろな難易度
・連結や損益分岐点分析/セグメント分析など実践的な内容を学べる。
特に2級は独学では難しいため、ビジネス会計検定講座の受講も検討してみてください。
以上より、3級合格後の選択肢としては、「2級に進む」ことがおすすめと言えます。
2) 株式投資
2つ目の3級合格後の選択肢としては、「株式投資」が考えられます。
ビジネス会計検定3級でいくら分析手法を学んでも、実際に使用しなければ、実践的なスキルは身に付きません。
普段から企業の財務諸表を見る習慣がある人であれば、3級で学んだ手法を実践する機会があるため、問題ないかと思います。
一方で、多くの人は普段の生活で財務諸表を意識的に読むことはなく、3級で学んだ内容を実践する機会が少ないです。
そんな人達に「今日から財務諸表を読んでみましょう!」といっても、多くの人が挫折してしまいます。
そこでおすすめしたいのが、少額の株式投資を始めてみることです。
少額でもお金がかかると、誰しも真剣になるものです。
実際に自分が投資するとなると、みなさん本気で財務諸表を見始めることでしょう。
この際に、ビジネス会計検定3級の知識が活きてきますし、実際に分析手法を使用することで、より財務諸表分析に対する理解が深まります。
以上より、3級合格後の選択肢としては、「株式投資」がおすすめと言えます。
9. 終わりに
いかがでしたでしょうか?
「会計のカの字も知らない…」と不安だった方も、3級からならチャレンジできそうですよね。
本記事を通してビジネス会計検定試験に興味を持ち、皆様のキャリアアップに繋げていただければ、とても嬉しく思います。
少しでも受験してみようかな、と思った方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください!
10. まとめ
◆検定で得られるスキルは、ビジネスシーンでも日常でも、広く役に立つ。
◆ビジネス会計検定3級の難易度は、決して高くない。
◆油断は禁物だが、合格すれば費用対効果は高い。
◆合格までの勉強時間は100時間が目安。