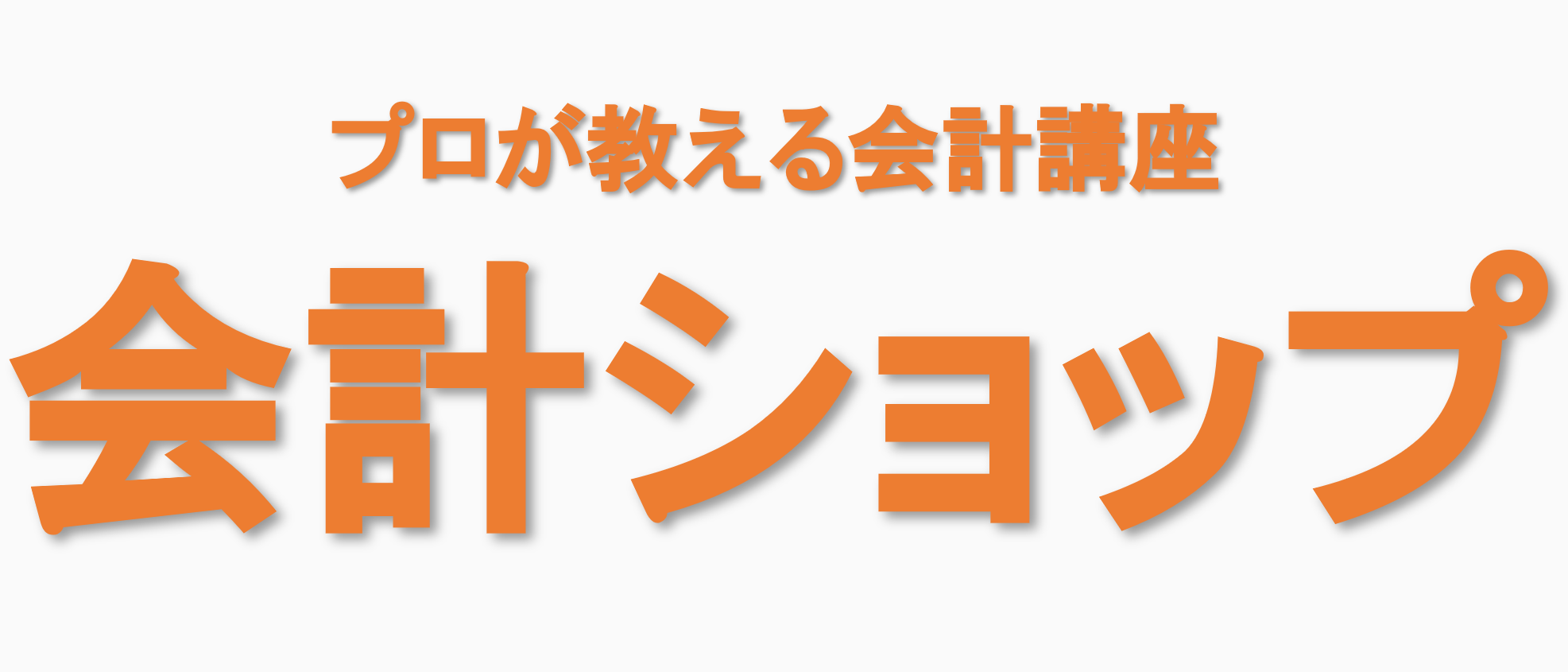簿記という言葉について、今まで耳にしたことがない人はほとんどいない、と言えるほど有名な簿記検定試験。
ただ、その必要性や取得によるメリットについて理解している人は、必ずしも多くないのではないでしょうか?
そこで今回は、簿記検定は役に立つのか?について解説していきます。
1. 簿記検定とは?
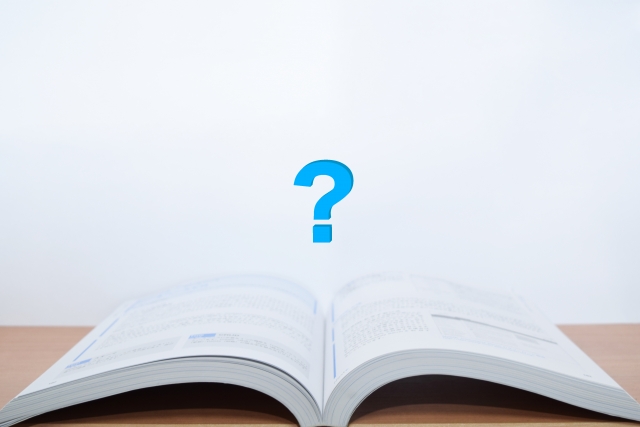
1) 簿記検定とは?
まず、そもそも簿記検定とは何なのか?という概要についてお伝えしていきます。
簿記とは、日々の経営活動を記録して、その企業の経営成績や財務状態を、客観的な数値で見えるようにするための技能を言います。
そして、簿記検定とは簿記の能力を測るために、日本商工会議所が主催する資格試験となります。
2) 実施級
① 簿記初級
2017年4月から実施されるようになったのが、簿記の超入門的な試験となる「簿記初級」です。
インターネットを介して行われるネット試験である点が特徴です。
かなり基礎的な試験となりますので、通常であれば簿記初級を飛ばして、簿記3級からの受験でも問題ございません。
② 3級
ビジネスパーソンとして押さえるべき、簿記の基礎知識を習得できるのが、「簿記3級」となります。
商業簿記の基本的な内容が、問われる試験となります。
③ 2級
経理などの簿記を必要とする職種において求められている、必須の知識を習得できるのが、「簿記2級」となります。
商業簿記だけでなく、工業簿記からの出題もあります。
④ 1級
簿記の知識としては非常に高度な内容を扱い、商業・工業簿記のみならず、会計基準や会社法などの各法規についても出題されるのが、「簿記1級」となります。
合格すると、税理士試験の受験資格を得ることができます。
3) 受験資格
受験資格はなく、いきなり2級や1級を受験することも可能です。
また、併願での受験も可能となります。
4) 試験時期
① 統一試験
| 簿記 検定 |
167回 | 168回 | 169回 |
| 試験日 | 2024 6/9(日) |
2024 11/17(日) |
2025 2/23(日) |
| 実施級 | 3~1級 | 3~1級 | 3~2級 |
② ネット試験(3級、2級)
随時受験可能。
5) 試験形式
① 統一試験
記述式試験。
② ネット試験
CBT方式。
6) 難易度・合格率
① 初級
| 期間 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 2023/4/1~2024/3/31 | 3,271 | 1,960 | 60% |
| 2022/4/1~2023/3/31 | 3,353 | 2,062 | 62% |
| 2021/4/1~2022/3/31 | 3,644 | 2,341 | 64% |
| 2020/4/1~2021/3/31 | 3,988 | 2,516 | 63% |
| 2019/4/1~2020/3/31 | 4,284 | 2,545 | 59% |
② 3級
・統一試験
| 回数 | 受験 者数 |
実受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 |
| 166 | 28,565 | 23,977 | 8,706 | 36% |
| 165 | 30,387 | 25,727 | 8,653 | 34% |
| 164 | 31,818 | 26,757 | 9,107 | 34% |
| 163 | 37,493 | 31,556 | 11,516 | 37% |
| 162 | 39,055 | 32,422 | 9,786 | 30% |
| 161 | 43,723 | 36,654 | 16,770 | 46% |
| 160 | 52,649 | 44,218 | 22,512 | 51% |
| 159 | 58,025 | 49,095 | 13,296 | 27% |
| 158 | 58,070 | 49,313 | 14,252 | 29% |
| 157 | 70,748 | 59,747 | 40,129 | 67% |
| 156 | 77,064 | 64,655 | 30,654 | 47% |
| 155 | 中止 | |||
| 154 | 100,690 | 76,896 | 37,744 | 49% |
| 153 | 99,820 | 80,130 | 34,519 | 43% |
| 152 | 91,662 | 72,435 | 40,624 | 56% |
・ネット試験
| 期間 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 |
| 2023/4 ~2024/3 |
238,155 | 88,264 | 37% |
| 2022/4 ~2023/3 |
207,423 | 85,378 | 42% |
| 2021/4 ~2022/3 |
206,149 | 84,564 | 41% |
| 2020/12 ~2021/3 |
58,700 | 24,043 | 41% |
③ 2級
・統一試験
| 回数 | 受験 者数 |
実受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 |
| 166 | 10,814 | 8,728 | 1,356 | 16% |
| 165 | 11,572 | 9,511 | 1,133 | 12% |
| 164 | 10,618 | 8,454 | 1,788 | 21% |
| 163 | 15,103 | 12,033 | 2,983 | 25% |
| 162 | 19,141 | 15,570 | 3,257 | 21% |
| 161 | 16,856 | 13,118 | 3,524 | 27% |
| 160 | 21,974 | 17,448 | 3,057 | 18% |
| 159 | 27,854 | 22,626 | 6,932 | 31% |
| 158 | 28,572 | 22,711 | 5,440 | 24% |
| 157 | 45,173 | 35,898 | 3,091 | 9% |
| 156 | 51,727 | 39,830 | 7,255 | 18% |
| 155 | 中止 | |||
| 154 | 63,981 | 46,939 | 13,409 | 29% |
| 153 | 62,206 | 48,744 | 13,195 | 27% |
| 152 | 55,702 | 41,995 | 10,666 | 25% |
・ネット試験
| 期間 | 受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 |
| 2023/4 ~2024/3 |
119,036 | 41,912 | 35% |
| 2022/4 ~2023/3 |
105,289 | 39,076 | 37% |
| 2021/4 ~2022/3 |
106,833 | 40,713 | 38% |
| 2020/12 ~2021/3 |
29,043 | 13,525 | 47% |
④ 1級
| 回数 | 受験 者数 |
実受験 者数 |
合格 者数 |
合格率 |
| 165 | 12,886 | 10,251 | 1,722 | 17% |
| 164 | 11,468 | 9,295 | 1,164 | 13% |
| 162 | 12,286 | 9,828 | 1,027 | 10% |
| 161 | 11,002 | 8,918 | 902 | 10% |
| 159 | 11,389 | 9,194 | 935 | 10% |
| 158 | 9,310 | 7,594 | 746 | 10% |
| 157 | 7,785 | 6,351 | 502 | 8% |
| 156 | 10,078 | 8,553 | 1,158 | 14% |
| 155 | 中止 | |||
| 153 | 9,481 | 7,520 | 735 | 10% |
| 152 | 8,438 | 6,788 | 575 | 9% |
7) 勉強期間
勉強時間は3級100時間、2級200時間程度が想定されます。
期間については「簿記3級・2級の勉強時間は?一ヶ月・二ヶ月での合格は可能?」をご参照ください。
1級については難易度が非常に高く、500~1,000時間は必要となります。
2. 簿記の必要性:どんな人の役に立つ?

1) 簿記3級の必要性
簿記3級はこんな人におすすめ!
・簿記2級の取得を検討されている方
・営業など経理以外で簿記の知識を活かしたい方
・「会計」や「経理」という分野の適性が自分にあるか知りたい方
簿記3級は全てのビジネスパーソンにとって、必須の知識となりつつあります。
何の職種であれ「会計」は英語などと同様に、ビジネスの共通言語と言えます。
特に年齢が若い方であれば、簿記3級を取得することで、経理職や会計事務所への就職・転職が可能です。
また、簿記2級の取得を検討されている方であれば、まずは簿記3級から取得することをおすすめいたします。
簿記2級は3級と比較してかなり難しく、土台となる3級の知識がしっかりと定着していないと、落ちてしまう可能性が高いです。
いきなり2級を受けるよりも3級⇒2級の方が、結果として勉強時間が短くなるので、まずは3級から受験するのがおすすめです。
さらに、「会計」や「経理」という分野に将来的にはかかわりたいと考えているけど、適性があるかどうか知りたいという方にも、簿記3級の受験はおすすめです。
向き不向きはあるので、気軽に受験できる簿記3級で試してみるのも、1つの方法です。
簿記初級は簡単すぎて、適正をはかることができない可能性があるため、できれば簿記3級が良いでしょう。
2) 簿記2級の必要性
簿記2級はこんな人におすすめ!
・簿記1級の受験を検討されている方
・他の資格と合わせて自分の武器にしたい方
・起業を考えている方
経理職など簿記を専門として扱う職業においては、簿記2級を必須としているところが多くあります。
逆に言えば、簿記2級を取得しておけば、経理職などの働き口の選択肢がいっきに増えます。
せっかく簿記の勉強を始めたのであれば、ぜひ簿記2級までの取得を検討してみてください。
また、後述のビジネス会計検定や建築業経理士など、他の資格と掛け合わせることで自身のスキルを上げたいと考えた場合も、簿記2級までの取得がおすすめとなります。
さらに、2級では工業簿記で原価計算を学ぶため、自身の会社の原価計算が必須となる、起業を考えている方にもおすすめとなります。
3) 簿記1級の必要性
簿記1級はこんな人におすすめ!
・会計のプロとして活躍したい方
簿記1級を取得することで税理士試験の受験資格を得ることができるため、税理士を目指されている方には役に立ちます。
また、会計の道でプロフェッショナルとして生きていく場合も、簿記1級が活躍することがあります。
ただ、2級までとは比べ物にならないほど難易度が高く、コストパフォーマンスが高い資格とは言えません。
そのため、税理士試験の受験資格を既に持っている方であれば、簿記1級を経由せずに税理士試験の勉強を開始された方が良いですし、また、会計のプロとして生きる場合も、本当に簿記1級まで必要なのかは慎重に判断する必要があります。
3. 簿記取得の5つのメリット!

1) 転職・就職で有利
簿記は経理職のみならず、他の職種でも転職や就職の際に、有利となることがあります。
厳密に言うと、簿記を持っている人が多数いるため、持っていないと他の候補者と差ができてしまうのですが、簿記を持っておくことでこの差をなくすことができます。
経理職であれば2級まで、その他の職種であれば3級までは取得しておきたいところです。
また、簿記の過程で身につけた知識・専門用語が、面接や応募企業の会社分析などに直接活きてくる、といった効果もあります。
2) キャリアアップに有効
社内でのキャリアアップにも、簿記は有利に働きます。
経理職や管理職の方であれば、昇給の要件となっている場合もあります。
経理職以外の方であれば、同僚と差をつけるチャンスです。
例えば、営業職やマーケティング職などは一見簿記とは関係ないように見えますが、取引相手やライバル企業を分析する際に売上高や利益など財務情報の分析が必要となり、売上高や利益がどのようにして作成されるのかという背景を知っておく必要があります。
エンジニアであれば、経理周りのシステムを開発・保守する必要もあり、経理の一連の流れを把握しておく必要があります。
また、近年では各部署を横断的に担当して、部署間の橋渡しとして活躍する社員も求められており、簿記を取得することで経理と他部署の橋渡しとしての活躍も期待できます。
3) 投資に役立つ
投資をする際に重要なことは、その企業が今後成長すると市場が見ているのか、成長しないと市場が見ているのかを把握することです。
そして、市場の各投資家が企業の成長性に関して重要視しているのが、決算書類の数値となります。
前期・市場平均と比べて当期の売上高・利益はどうだったのか?などの判断材料は財務諸表に記載されており、この財務諸表を作成するスキルが簿記となります。
投資の判断材料となる財務諸表の作成ロジックを理解しておくことで、より確度の高い投資判断を行うことができます。
4) 起業の際に役に立つ
起業の際に会社の売上や利益・キャッシュの流れを把握しておくことは、経営者に当たり前に求められます。
近年ではクラウド会計システムが発達しており、必要な項目を入力すれば自動で仕訳を切ってくれます。
そのため、財務数値を作成するのに特殊な知識は必要ないように思えますが、1つ1つの仕訳は専門用語で記載されており、最低限の専門用語を覚えないとそもそも作成された数値を読むことができません。
また、特に起業当初はビジネスモデルも毎月・毎年変更する可能性があり、非定型的な取引が起こることが多く、事前にクラウド会計システムに入力した項目では対応できないことがあります。
この際にも、簿記の知識は必要となります。
5) ビジネスの共通言語を身につけられる
「会計」はビジネスにおいて、世界的に共通言語となりつつあります。
取引先や提携先の担当者と商談をする上で、いちいち個々の財務数値がどのように作成されているのかを説明することはありません。
つまり共通言語とは「知っておいた方がいいこと」ではなく、「知っておかないと損をすること」であり、簿記取得は国内のみならず、国際的に活躍する上で必須の要件となりつつあります。
簿記講座の元運営責任者が、「講座代金(安さ)」と「講座との相性(わかりやすさ)」の観点から、おすすめ通信講座を以下の5つに絞り、メリット・デメリットについて解説してみました。
・クレアール
・フォーサイト
・ネットスクール
・CPA会計学院
・スタディング
詳細は「簿記の通信講座おすすめ5選!安さとわかりやすさで比較すると..」をご確認ください。
4. 同時取得&ステップアップ資格!おすすめ5選

1) ビジネス会計検定
1つ目の同時取得おすすめ資格は「ビジネス会計検定」です。
簿記とビジネス会計検定の関係の詳細については「ビジネス会計検定と簿記検定の共通点、相違点は?」をご確認ください。
簿記で財務諸表を「作成する力」を身につけるだけでなく、ビジネス会計検定で財務諸表を「分析する力」を身につけることで、企業のお金の流れを読むことができ、経理・営業・マーケティング・企画などあらゆる職種で活躍できる武器を手にすることができます。
2) ファイナンシャルプランナー
金融業界にお勤めの人や、個人で独立してフリーランスとして活躍したい人には、「ファイナンシャルプランナー」もおすすめです。
ファイナンシャルプランナーは資産形成などの個人のお金の専門家としての知識を身につけることができ、独立して活躍される方も多いです。
フリーランスとして活躍する場合も起業の場合と同様に、自身の事業の会計数値を把握しておく必要があるため、簿記の知識は必要となります。
ファイナンシャルプランナーの詳細については、「FP3級、2級で学べることとは?勉強するべき内容は多い?」をご参照ください。
3) 建設業経理士
簿記の中でもさらに専門性を極めて他者と差別化を図りたい場合は「建築業経理士」がおすすめです。
建設業周りの簿記に特化した資格が建設経理士であり、全国でインフラの整備が盛んな昨今、働き口も比較的多く人気の資格です。
建設業経理士の詳細については、「建設業経理士2級の難易度は?独学でも合格できる?」をご参照ください。
4) 公認会計士
難易度は一気に上がりますが、簿記からのステップアップとして「公認会計士」もおすすめです。
独占業務である監査業務もあり、また、登録すれば税理士業務もできるため、資格を取得すれば仕事に困ることはあまりないです。
公認会計士試験の試験科目である会計学の中に簿記が含まれており、簿記の勉強がそのまま公認会計士試験の勉強につながります。
ただ、数年間勉強し続ける覚悟が必要であり、費用対効果をしっかり考えて臨む必要があります。
5) 税理士
公認会計士同様に非常に難易度が高いですが、簿記1級を取得することで受験資格が得られる、税理士もおすすめの資格となります。
公認会計士と異なり1科目ずつ受験することができるので、まずは簿記1級と親和性のある簿記論・財務諸表論の勉強から開始するのがおすすめです。
ただ、1科目ずつ取得できる反面、全科目を一斉に取得することはほぼ無理であり、公認会計士試験以上に合格まで長い年月が必要となります。
2023年度の税理士試験より、簿記論・財務諸表論の受験資格が撤廃され、誰でも受験できるようになりました。
簿記論・財務諸表論は、税理士試験で多くの受験生がまず受験を考える科目であるため、非常に受験しやすくなったと言えます。
5. 終わりに
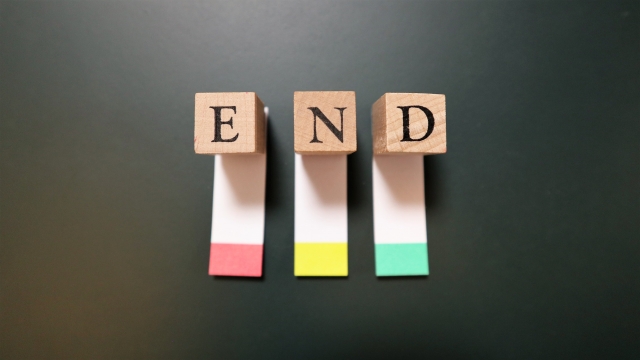
いかがでしたでしょうか?
簿記検定はいろいろな局面で役に立ち、取得することで多くのメリットを得ることができるため、この機会にぜひ取得を検討してみてください。
また、相性のいい他の資格についても簿記の勉強と合わせて受験を検討してみてください。
6. まとめ
◆簿記1級は税理士試験の受験資格を得ることができるが、費用対効果を考えて受験を検討すべき。
◆簿記は転職や起業、キャリアアップや投資など、多くの局面で役に立つ。
◆ビジネス会計検定や建設業経理士など相性のいい資格の取得も検討する。