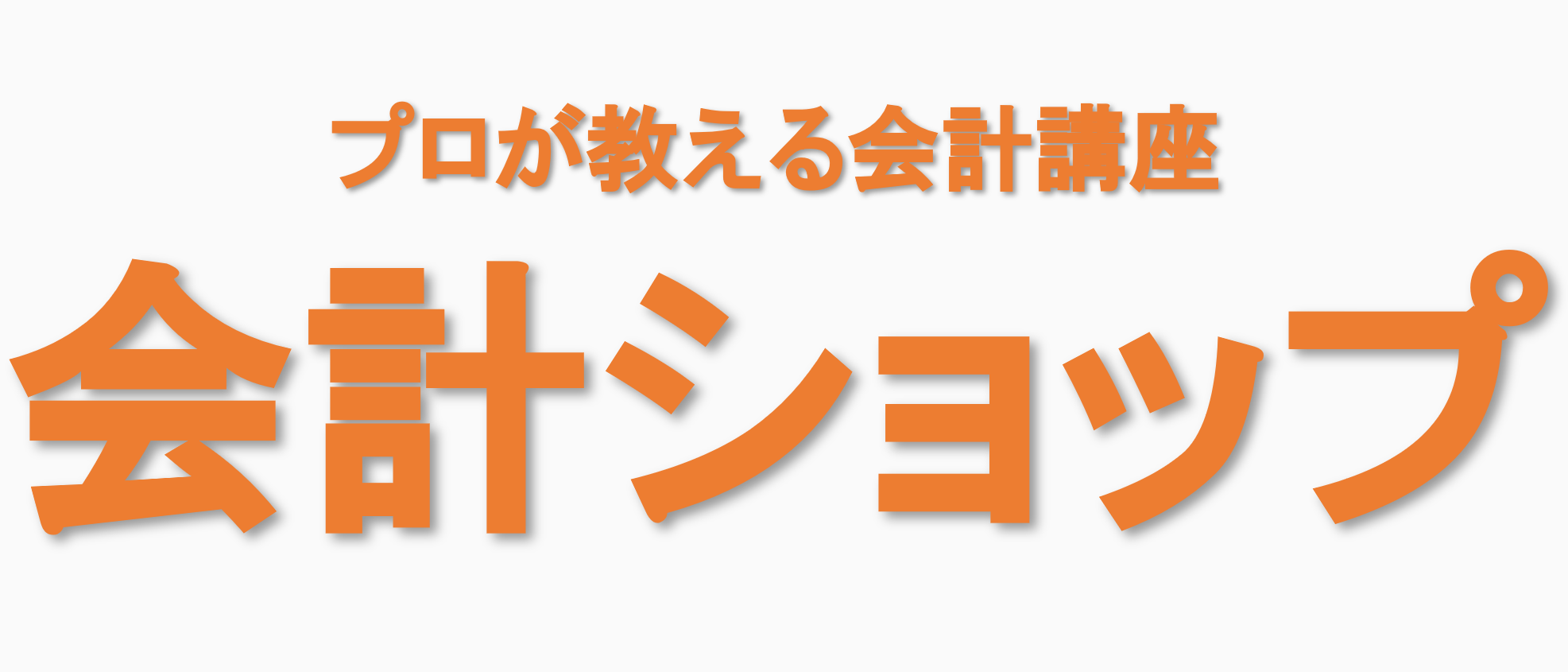「FP受検を考えているけど、何級から受検すべきかわからない..」
「2級から受検しても問題ないの?」
今回はこのような疑問を解決していきます。
結論から言うと、FP受検で何級から勉強すべきか迷っている人には、3級からの受検がおすすめです。
主な理由として、FP2級には受検資格があったり、そもそも2級の難易度が高くて、挫折してしまう可能性があることが挙げられます。
ただ、経験や知識によっては、2級から受検しても問題ないケースもあります。
・FP受検は3級から始めるべき理由
・2級から受検しても問題ないケース
以上の2点に絞って、詳しく解説していきます。
FP資格を取得して会社で活かしたい、家計管理に役立てて生活を良くしたいという人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. 3級から勉強すべき4つの理由
1) 2級には受検資格の制限があるから
2) 向き不向きを判断できるから
3) 効果的な勉強ができるから
4) 日常に活かすなら3級で十分だから
2. 2級からでも問題ない4つのケース
1) 2級の受検資格を満たしている場合
2) ある程度金融知識を持っている場合
3) 過去に勉強で成功体験がある場合
4) 挫折しない自信がある場合
3. 終わりに
4. まとめ
1. 3級から勉強すべき4つの理由

1) 2級には受検資格の制限があるから
FP3級から勉強すべき1つ目の理由は、「2級には受検資格の制限があるから」です。
誰でもいきなり、2級を受けられるわけでありません。
FP2級の受検資格は、大きく分けて4つあります。
② FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
③ 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
④ 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者
① FP3級技能検定の合格者
FP3級の合格者は、2級の受検資格を得ることができます。
2級の受検申請時に、3級の合格番号の提出を求められます。
② FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
・証券会社、保険会社、銀行、クレジット会社などの金融機関に勤務している方
・保険会社(代理店)の職員
・税理士、弁護士、司法書士、行政書士などで、資産に関する相談業務に従事している方
・会計事務所の職員
・不動産会社、建設会社など土地建物取引・建築・相談業務に従事している方
・投資顧問会社の職員
・生活協同組合などの共済等の担当職員
・商品先物取引会社の職員
・一般事業会社および官公庁の福利厚生担当者および、金融・財務・経理担当者
・商事会社の商社金融担当者、商事会社やコンピュータ会社等の金融機関営業担当者および、ソフト開発担当者
以上のような経験を積んでいれば、実務経験としてみなされます。
銀行や証券会社、保険会社は納得でしょう。
他にも、不動産業務や経理の仕事も、実務経験になります。
知らない間に実務経験をクリアしていたということもあるので、自分の職歴が実務経験としてカウントされるのか、確認しておきましょう。
期間は連続していなくても構いません。
1年銀行に勤めて退職した後、5年後に1年間経理で働いても、実務経験は2年になります。
また、実務経験は必ずしも正社員である必要はありません。
派遣社員やアルバイトでの就労経験も、実務経験としてみなされます。
③ 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
AFP認定研修は、FP協会が認定している研修講座です。
「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「相続・事業承継設計」「リスクと保険」「タックスプランニング」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」の6つの専門分野があり、ファイナンシャルプランニングに必要な知識を網羅的に学習できます。
DVDやインターネット学習など、通信教育がメインです。
場所や時間に縛られないので、自分の好きなタイミングで勉強できます。
受講できる教育機関は、「生涯学習のユーキャン」や「資格の学校 TAC」、「資格の大原」など20社以上です。
研修形態やカリキュラム、学習にかかる期間は教育機関によって違うので、自分の目的やライフスタイルに合わせて、適しているところを選ぶ必要があります。
研修の詳細については、各社のホームページから確認できます。
④ 厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者
厚生労働省認定金融相技能審査は、2001年で認定が終了しています。
2001年以前に取得していた人は、FP2級の受検資格として有効です。
ただ、20年ほど前なので、詳しい説明は省いておきます。
ここまで受検資格を紹介してきましたが、FP資格を初受検するタイミングで、実務経験が2年超えている人は少ないでしょう。
また、AFP認定研修を修了するのはそれなりに大変なので、まずは3級から受検するのが一般的です。
(受検資格については「いきなり2級受検は不可?受検資格は?」も合わせてご確認ください。)
2) 向き不向きを判断できるから
FP3級から勉強すべき2つ目の理由は、「向き不向きを判断できるから」です。
FP協会ときんざいの2団体の合格率を合計すると、3級は約70%あります。
一方で2級になると、大きく下がって約30%です。
いきなり2級を受検しても、難易度が高く途中で挫折してしまうかもしれません。
せっかく勉強を始めても、途中で挫折してしまうと資格は取得できず、勉強した時間は無駄になってしまう可能性があります。
まずは3級を受検して、FP資格に対する「向き不向き」を判断するのがおすすめです。
3) 効果的な勉強ができるから
FP3級から勉強すべき3つ目の理由は、「効果的な勉強ができるから」です。
FP3級と2級では、試験内容に大きな差はありません。
3級と同じ範囲の中で、より深く詳しい知識を求められるのが2級です。
3級で先に全体像を把握してから細部の勉強をすることで、相互に関連している内容や似ている内容を、体系的に理解できます。
そのため、まずは3級を勉強して全体像を押さえた後に、2級を勉強する方が効果的です。
3級の知識が残っているうちに2級の勉強を始める方が勉強時間を削減できるので、3級を取得したらできるだけ早く、2級も勉強しましょう。
4) 日常に活かすなら3級で十分だから
FP3級から勉強すべき4つ目の理由は、「日常に活かすなら3級で十分だから」です。
資格を取得するなら、「できるだけ難易度が高いものを取得しておくべきではないか?」と思う人もいるでしょう。
ただ、金融機関勤務など実務で活かしたい人以外は、3級の知識で十分です。
なぜなら、3級で学ぶ内容だけでも、十分日常生活で役立つからです。
仮に3級の内容では足りないと感じた分野があったとしたら、その分野だけ2級の勉強をしてみるのもおすすめです。
2級の方が3級より当然に難しく、その分だけ多くの勉強時間が必要になります。
家計の見直しなど、日常生活に活かすためだけに2級を取得するのは、必要な勉強時間を考慮すると、割りにあわない人も多いはずです。
FP講座の元運営責任者が、以下の7つの通信講座を比較して、おすすめ4つのメリット・デメリットや、講座の特徴について解説してみました。
・TAC
・大原
・LEC
・ユーキャン
・フォーサイト
・アーティス
・ECC
詳細は「FPの通信講座おすすめ4選:FP講座の元運営責任者が解説します!」をご確認ください。
2. 2級からでも問題ない4つのケース
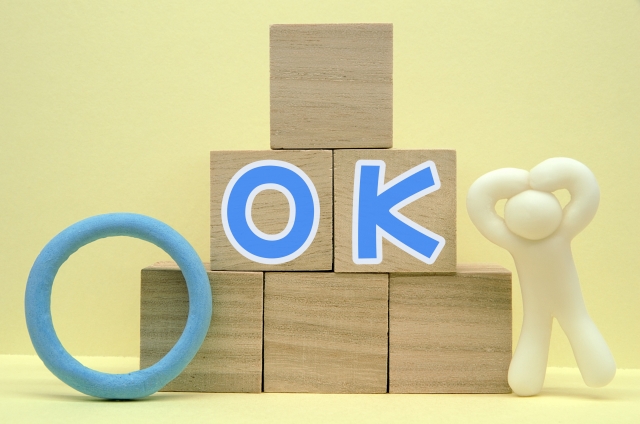
1) 2級の受検資格を満たしている場合
FP2級からでも問題ない1つ目のケースは、「2級の受検資格を満たしている場合」です。
「AFP認定研修修了者」や「2年以上の実務経験がある人」は、2級からの受検で問題ありません。
すでに金融知識や経験は豊富なので、勉強に挫折する可能性は低いでしょう。
FP試験の難しいポイントの一つに、聞きなじみのない単語がいくつも登場することが挙げられます。
知らない単語ばかりでてくる問題集を解き続けるのは、かなり大変でしょう。
しかし、実務経験があったりAFP認定研修を修了した人にとっては、聞いたことのある単語も多いでしょう。
語句を知っているだけでも、勉強のスタートダッシュはスムーズです。
また、FP試験は年に3回しか行われていません。
初めから2級を受ければ、取得にかかる期間は短くなります。
しかし、3級を受けてから2級を受ける場合、次の試験は4か月ほど先になってしまうので、どうしても取得までの期間は長くなってしまいます。
すでに持ち合わせている知識があるなら、できるだけ早く取得できる方を目指しましょう。
2) ある程度金融知識を持っている場合
FP2級からでも問題ない2つ目のケースは、「ある程度金融知識を持っている場合」です。
仕事で2年以内ながら専門的な実務経験を積んでいたり、家計管理や大学などの日常生活を通して、一定程度の金融知識をすでに有していたりする場合は、2級から取得しても問題ありません。
ただ、この場合に問題になのが、受検資格です。
AFP認定研修として指定を受けている講座を受講、修了し、受検資格を得て2級を受検するか、2級の勉強をした後にまず3級を受検して、合格後に2級を受検する方法もあります。
3級のCBT試験が開始され毎月受検できるようになったため、3級に合格して2級の受検資格を得る方が現実的です。
3) 過去に勉強で成功体験がある場合
FP2級からでも問題ない3つ目のケースは、「過去に勉強で成功体験がある場合」です。
国立大学や有名私立大学に入学していたり、難関試験に合格していたりする人はm勉強に対する苦手意識が比較的少ないでしょう。
FP2級は3級と比べると高い難易度ですが、3級を保有していなければ手も足も出ないというわけではありません。
大学入試や資格試験の成功体験がある人は、勉強スタート時は知らない単語ばかりで苦戦するかもしれませんが、試験勉強を乗り越えられるのではないでしょうか。
4) 挫折しない自信がある場合
FP2級からでも問題ない4つ目のケースは、「挫折しない自信がある場合」です。
FP2級は3級以上の勉強時間を確保しなければならず、200時間程度は必要と言われております。(「FP3級と2級の勉強時間はどのくらい?何か月で合格できる?」参照。)
200時間の勉強時間を確保するため必要な期間の目安は、以下の通りです。
① 平日仕事終わりに2時間勉強する場合
10時間×20週=200時間
平日2時間の勉強を継続する場合は、取得までに4か月~5か月ほどかかります。
② 休日に4時間勉強する場合
8時間×25週=200時間
土日の4時間勉強する場合、5か月~6か月ほどかかります。
会社員をしながら上記の勉強時間を確保し続けるのは、非常に難しいことです。
仕事から疲れて帰ってきても勉強できる!という人であれば問題ないかもしれませんが、4か月~6か月ほど毎日勉強を継続し続けるのは、一般的には難しいです。
一方で、学生や仕事の負担が少ない人、休職している人など継続的に勉強時間を確保できて、挫折しない自信があるという人は、2級から受検しても問題ありません。
ただし、時間が確保できても挫折してしまうかもしれないと思う人は、3級から取得を目指しましょう。
無理のない範囲で、一歩ずつ勉強を進めていくことが大切です。
3. 終わりに
ここまで、初めてのFP受検は3級から始めるべき理由を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
いきなりレベルの高い2級から受検を始めてしまうと、挫折してしまうかもしれません。
せっかくFPを志しても、途中でやめてしまうともったいないです。
まずは、難易度や適性を見極めるという意味でも、FP3級から受検してみましょう。
ただ、すでに実務経験を2年以上積んでいたり、金融に対する知識を豊富に持っていたりする場合は例外です。
自分の知識や目的に合わせて、何級から受検するのか選んでいきましょう。
もし、それでもどちらから受検すれば良いか分からないという人には、3級から受検するのをおすすめします。
4. まとめ
◆2級には受検資格があり、最初から満たしている人は少ない。
◆3級から受検すればFP資格の向き不向きを確認できる。
◆3級の後に2級を受検すれば効率的に勉強を進められる。
◆日常生活に活かす程度なら3級で十分。
◆すでに2級の受検資格を満たしていれば、いきなり2級でも問題なし。
◆ある程度の金融知識を持っているならば、最初から2級を受けるのも選択肢の一つ。
◆大学受検や資格試験で大きな成功体験がある人も、初めから2級を受けても良い。
◆勉強する時間が確保できて、挫折しない自信がある人も2級から受けてOK。