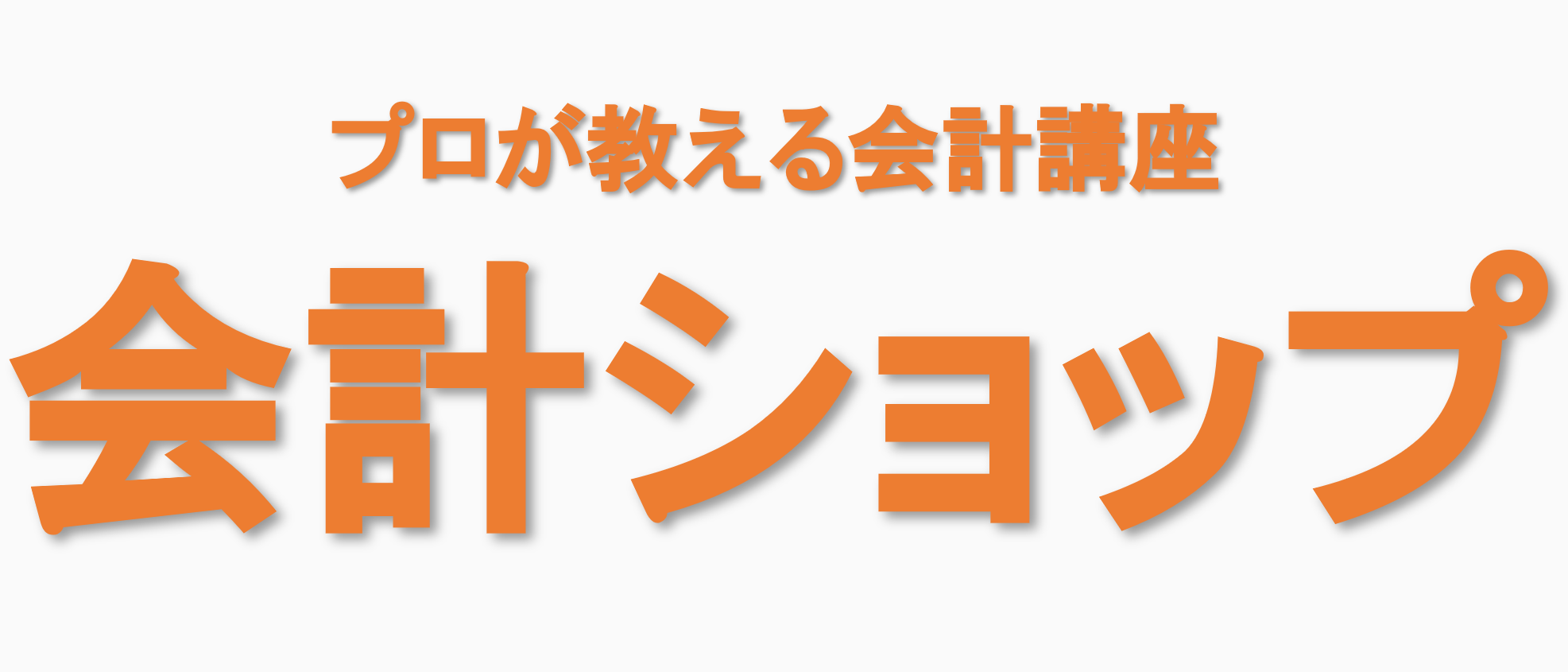中小企業診断士は、最終合格率が4%~8%程度の難関資格です。
合格するには膨大な勉強が必要ですが、日本で唯一の経営コンサルタント系国家資格であり、幅広いビジネススキルを持っていることの証明にもなるため、根強い人気があります。
受験者層はビジネスパーソンがメインではあるものの、学生や定年を迎えた人達が興味を持つことも多く、近年、受験者数は増加傾向にあります。
しかし興味はあっても「受験してみたいけど自分でもチャレンジできるのだろうか?」「学歴や実務経験が必要なんじゃないの?」と不安に感じる人も、一定数いらっしゃいます。
そこで今回は、中小企業診断士の受験資格に焦点を当てて、解説していきます。
1. 1次試験の受験資格
1) 受験資格はない
2) 科目免除はある
2. 2次試験の受験資格
1) 筆記
2) 口述
3. 受験資格がないメリット・デメリット
1) メリット
2) デメリット
4. 終わりに
5. まとめ
1. 1次試験の受験資格

1) 受験資格はない
「第1次試験の受験資格は、年齢、学歴等に制限はありません。」
中小企業診断協会の試験案内にははっきりとそう書かれており、受験資格はありません。
年齢、性別、学歴、実務経験、そして国籍までも不問です。
中小企業診断協会が発表している統計資料をみても、20歳未満の若年層から70歳以上の高年層まで、実に幅広い年代の方々がこの試験を受験されています。
そして、令和5年の1次試験最年少合格者は18歳、最高齢合格者は83歳でした。
かつては18歳~19歳が最年少、70歳前後が最高齢でしたから、合格者の年齢層も幅広くなってきています。
勤務先は民間一般企業が圧倒的に多く、次に金融機関、自営業者、学生、公務員などが続きます。
このように、中小企業診断士試験は、何歳の人であろうが、どこに勤めていようが、どこの国籍であろうが関係なく受験できます。
ただし、注意点が一つ。
それは、「受験資格はないが、中小企業診断士として登録するにはいろいろと条件がある」ということです。
その条件は、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」に定められており、例えば、未成年者は登録できません。
14歳の1次試験合格者が2次試験を突破できたとしても、中小企業診断士として活動はできないことになっています。
2) 科目免除はある
科目免除とは、一定条件を満たしている人のみ、特定科目の受験を免除する制度です。
中小企業診断士試験の場合、科目免除は主に2パターンあります。
一つは「他資格等保有による免除」という、保有資格や職業によって、特定科目の受験が免除してもらえる制度。
この制度では、公認会計士や税理士、あるいは弁護士、情報処理技術者といった特定の資格を保有している場合や、大学教授の仕事に3年以上就いているような場合に、それぞれ対応した科目の受験が免除されます。
そしてもう一つが「科目合格による免除」。
これは科目ごとに合否判定を行い、合格基準を満たした科目は翌年と翌々年の受験を、申請により免除してもらえる制度です。
科目合格制度については、詳細を「中小企業診断士:1次試験の科目合格戦略メリット・デメリット」で解説していますので、ご参照ください。
いずれのパターンも、科目免除を利用することで他の科目へ勉強時間を割り振ることができる、というメリットがあります。
しかしその反面、得点できる可能性が高い科目を捨てることになるので、全体の平均点が下がるリスクがあります。
使いどころに注意が必要です。
2. 2次試験の受験資格
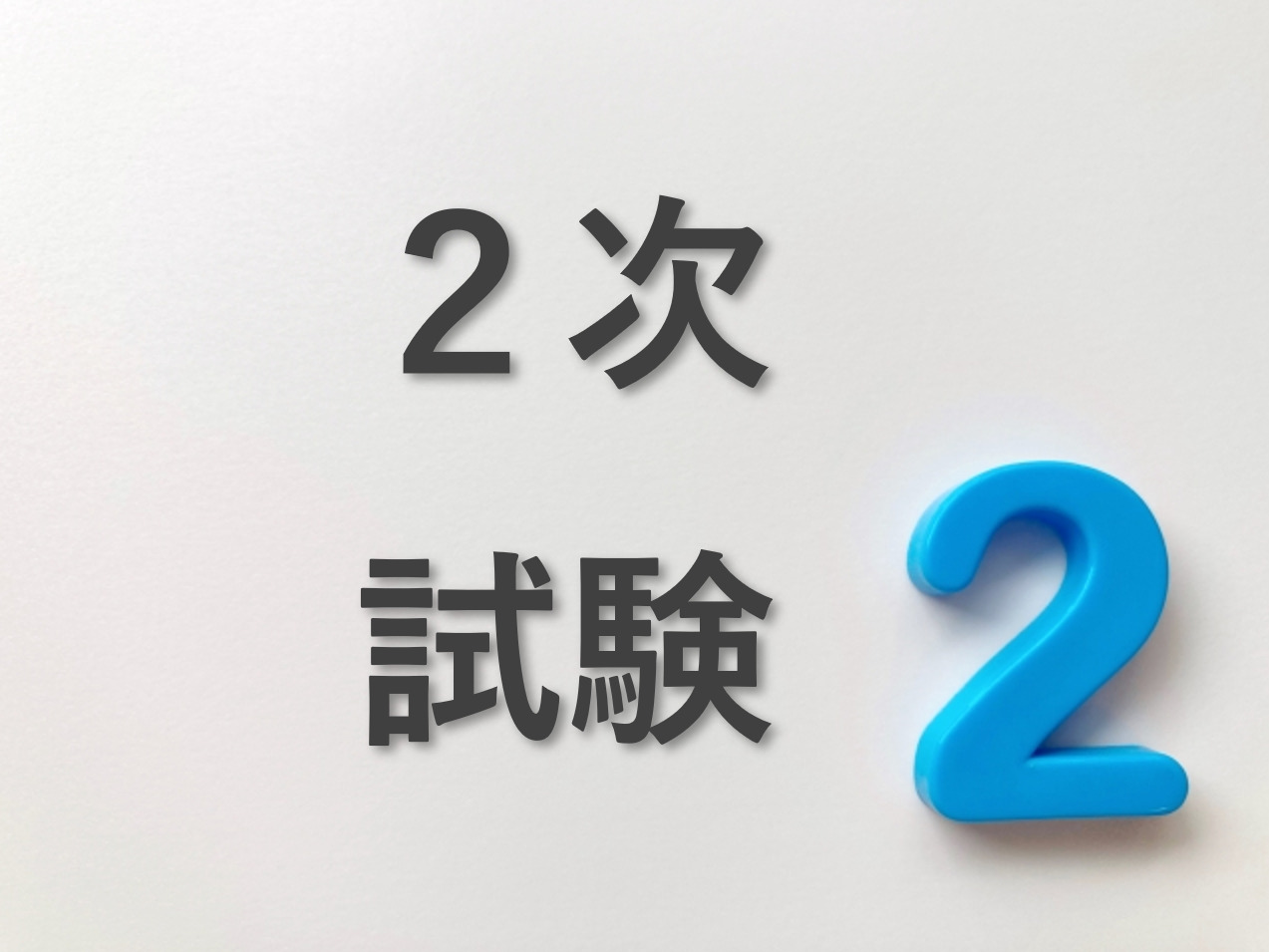
1) 筆記
2次試験の受験資格は「1次試験に合格していること」です。
また、1次試験の時にあった科目免除という制度は、2次試験にはありません。
1次試験の点数がどれほど良くても、あるいは関連性の高い難関資格を保有していても、全科目受験して合格点を取る必要があります。
そして、1次試験の合格には有効期間があります。
有効期間は合格した年とその翌年の2年間。
つまり、今年の1次試験に合格したのであれば、来年の1次試験は免除となります。
また、1次試験は一度合格すると、それまでの科目合格の履歴がすべてリセットされます。
有効期間内に2次試験に合格できなければ、1次試験を一から受験し直さなくてはなりません。
1次試験の免除についてはもう一点、特例制度があります。
「平成12年度以前の1次試験合格者」は、一回に限り、1次試験をパスして2次試験から受験することが認められる、という内容です。
2) 口述
口述試験の受験資格は「筆記試験を合格していること」です。
口述試験も免除などの制度はありませんが、筆記試験の内容を基に出題されるため、例年、合格率はほぼ100%で推移しています。
中小企業診断士講座の元運営責任者が、以下の7つの通信講座のコストパフォーマンスを比較して、おすすめ2つのメリット・デメリットについて解説してみました。
・TAC
・スタディング
・診断士ゼミナール
・クレアール
・LEC
・アガルート
・フォーサイト
詳細は「中小企業診断士の通信講座おすすめ2選!元講座運営者が比較します」をご確認ください。
3. 受験資格がないメリット・デメリット
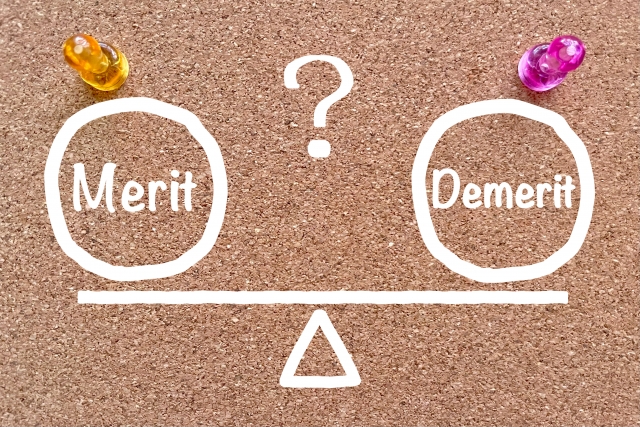
前述の通り、中小企業診断士の1次試験には、受験資格がありません。
それでは、受験資格がないことには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
順に解説していきます。
1) メリット
① すぐに勉強を開始できる
資格の中には受験資格として、様々な条件を設けているケースもあります。
例えば、建築士は学歴や実務経験が必要ですし、看護師も養成施設で学ばなければ受験できません。
他にも、社会保険福祉士やキャリアコンサルタントなども、実務経験や講習の修了が必須となります。
これに対し、中小企業診断士の試験には、受験資格がありません。
思い立ったらすぐに参考書などを買いそろえて、勉強をスタートさせることができます。
その気になったらすぐに走り出せるのは、大きなメリットだといえるでしょう。
② 短期合格が可能になる
すぐに勉強をスタートできるということは、短期合格を目指せるということでもあります。
もし、受験資格に実務経験3年以上といった条件があれば、最低でも3年間という時間が必要になってきます。
大卒が条件なら、最低でも4年は必要です。
しかし、中小企業診断士の試験には、そういった条件がありません。
極端なことを言えば、春の申し込み時期に受験を思い立って申し込み、夏の1次試験と秋から冬に行われる2次試験にストレート合格してしまうことも、理論上は可能です。
ちなみに一般的には、中小企業診断士の合格には、1,000時間の勉強が必要とされています。
1,000時間となると1年以上の勉強時間が必要になってきますが、驚くことに、たったの200時間で合格したという「ツワモノ」もいます。
200時間ということは毎日3時間勉強したとして67日、あるいは平日3時間、土日に8時間ずつ勉強したとしたら1か月半です。
こういう奇跡的な短期合格を目指せるのも、受験資格がない大きなメリットだといえます。
(勉強時間については、「中小企業診断士の勉強時間は1,000時間?半年合格は無理?」も合わせてご確認ください。)
③ 大学生や中高生でもチャレンジできる
中小企業診断士試験には年齢制限もないので、何歳からでも受験ができます。
ということは社会人である必要はなく、学生でも定年後の高齢者でも受験が可能となっています。
実際、14歳の中学生や80歳を越える高齢者が1次試験を受験し、見事合格を勝ち取っています。
ただし、中小企業診断士と名乗るためには、中小企業庁に登録されなければいけません。
既述の通り、規則で未成年者は登録を拒否されますし、高齢で認知機能に問題がある場合もやはり登録を拒否されます。
④ 受験者が多く情報が手に入りやすい
中企業診断士試験には、毎年多くの人が申し込みをしています。
ここ5年の申込者数は常に2万人を超え、受験者数も直近で16,000人を超えてきました。
| 申込者数 | 全科目受験者数 | |
| 令和元年度 | 21,163人 | 14,691人 |
| 令和2年度 | 20,169人 | 11,785人 |
| 令和3年度 | 24,495人 | 16,057人 |
| 令和4年度 | 24,778人 | 17,345人 |
| 令和5年度 | 25,986人 | 18,621人 |
(中小企業診断協会統計データより)
SNSによる情報発信が当たり前になっている昨今、これだけたくさんの人たちが受験していれば、それに比例するように試験について情報発信をする人も増えています。
例えば、資格学校が実施している模試の直後には、「思ったよりもできなかった」「〇〇科目は他の人もできてないみたいだから安心した」といったポストが多く流れてきますし、先輩診断士から「本番当日は時計を忘れがちだから気を付けて」「マスクを着用したままでの受験に慣れておくこと」「昼食はできれば前日のうちに用意しておいて」などの具体的なアドバイスを見つけることもできます。
こうした情報は資格学校が発信する情報とはまた違った「生の声」ですから、「なるほど!」と気づかされることも多いものです。
SNSに振り回されないよう注意も必要ですが、適度に距離を保ちつつ情報収集すると、メンタルの支えにもなります。
2) デメリット
① ライバルが多い
メリットと表裏一体ではあるものの、誰でも受験ができるということは、それだけライバルが増えやすいということにつながってきます。
特に最近は20歳未満の受験者数の増加が目立っており、2017年~2021年の受験者数推移では、全年代を通して、唯一、受験者数が増え続けています。
その他の世代も40代以降を中心に増加傾向にあり、ライバルが今後も増えていくことは、ある程度覚悟しなければなりません。
ただ、中小企業診断士試験には、合格者の定員がありません。
「合計得点が6割以上で4割未満の科目がないこと」という基準で合否判定されますから、ライバルの増加を必要以上に怖がる必要はありません。
② 向き不向きを判断しにくい
例えば、簿記やファイナンシャルプランナーの資格は、等級制度を導入しています。
勉強内容がもっとも簡単なのが3級、3級よりもさらに広い知識を問われるのが2級、2級のさらに上、一番難しいのが1級という具合です。
こうした「等級がある資格」の良いところは、気軽にチャレンジできるところです。
入門編ともいえる3級から始めれば、時間も費用もさほどかかりません。
万一、「勉強してみたけど自分にはあまり向いてないかな。」と挑戦をやめたとしても、さほどダメージはないでしょう。
しかし中小企業診断士の場合、等級制度はなく、いきなり最上級のレベルに挑戦するようなものです。
気軽にやって合格できるような難易度ではなく、時間も費用もかけ、生活パターンを受験シフトに変えていかなければなりません。
勉強期間が1年、2年と続くことも珍しくはなく、そこまでやっても合格できずに挫折してしまう人がたくさんいます。
そうなると、かなり長い時間を棒に振ることになります。
このように、受験資格がないというのは段階的なチャレンジができないということであり、相応のリスクもはらんでいます。
4. 終わりに
以上、中小企業診断士の受験資格についてまとめてきました。
受験資格がないというのは、短期合格が目指せたり、学生でも受験できたりとメリットがいくつもあります。
受験のハードルが低いので誰でも気軽にチャレンジできますが、合格のハードルはとても高く、根気強く勉強を継続する必要があります。
そして継続性を確保するためには、出来るだけ負担を減らすことが重要で、そのためには効率的な受験対策は不可欠です。
勉強方法や情報収集などは、上手に立ち回りましょう。
5. まとめ
◆要件を満たせば一部科目の受験を免除してもらえる。
◆実務経験不要で受験できるので短期合格を目指せる。
◆年齢制限がないので学生でも合格を目指せる。
◆受験者が多いので役立つ生の情報があふれている。
◆誰でも受験できるのでライバルも多くなる。
◆気軽に始められるが途中挫折する可能性も低くない。