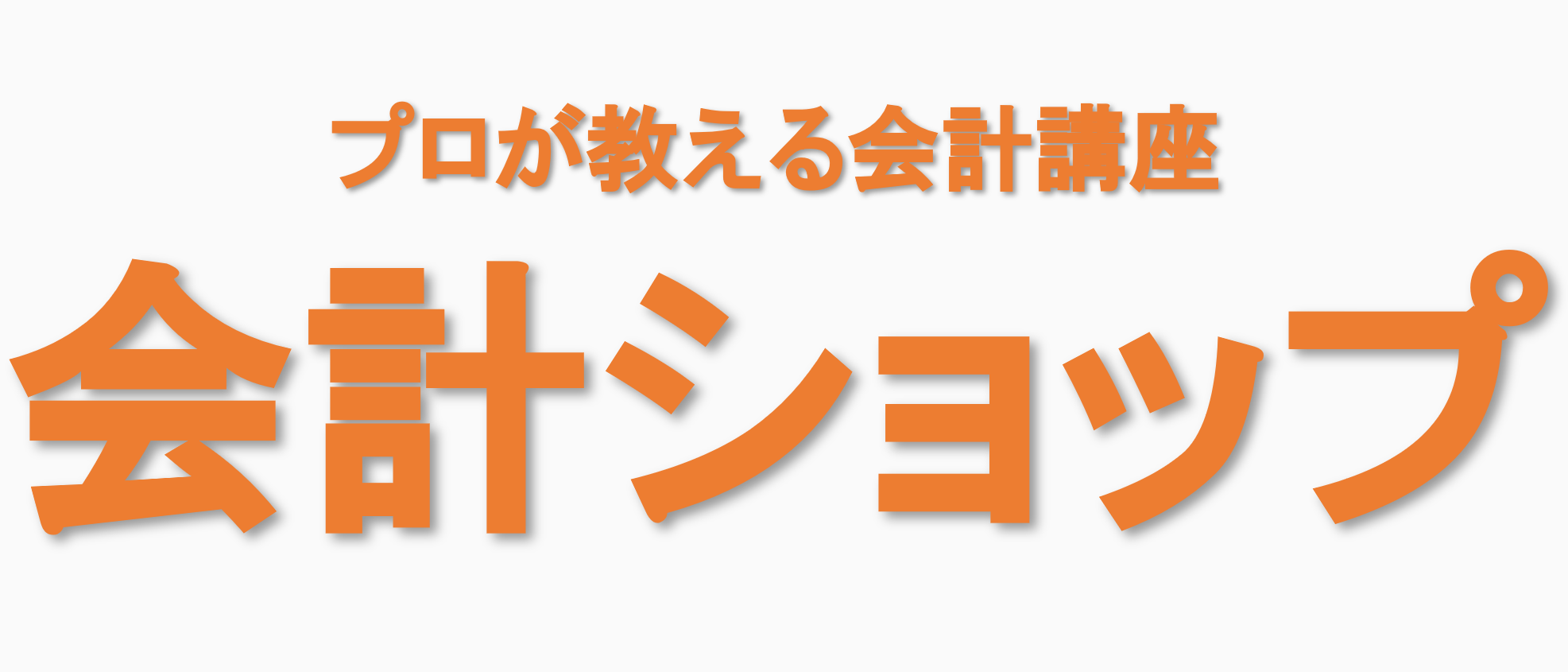ファイナンシャルプランナー試験の受験を検討する際に、FP技能士・AFP・CFPの3つの違いについて、皆様一度は悩まれるかと思います。
そこで今回は、FP技能士・AFP・CFPの違いについて解説していきます。
3つの違いをしっかり理解した上で、ご自身が取得すべき資格はどれなのか?取得する順番はどうするのか?といった点を考えてみてください。
1. FP技能士とAFP・CFPの違いは?

1) 主催団体の違い
| 資格名称 | 試験主催団体 |
| FP技能士 | FP協会・きんざい |
| AFP・CFP | FP協会 |
FP技能士は「日本FP協会」と「きんざい」が主催している国家資格であるのに対して、AFPとCFPは「日本FP協会」のみが主催している民間資格となります。
2) FP技能士とは?
FP技能士は3級から1級までで構成されており、一般的に「FP3級」「FP2級」と言われる場合には、「FP技能士3級」「FP技能士2級」のことを指します。
各級の概要については以下をご参照ください。
FP3級:「ファイナンシャルプランナー3級の難易度は?簿記3級より難しい?」
FP2級:「ファイナンシャルプランナー2級の難易度/合格率は?3級と何が違う?」
FP協会ときんざいの2つの団体どちらで受験しても、合格すれば同じFP技能士となり、差はありません。(実技試験の内容が異なるなど、試験内容の差はあります。)
FP技能士は一度取得してしまえば、更新の必要はなく、永続的に使用できる資格となります。
3) AFPとは?
① AFPとは?
AFPはFP技能士2級に相当する資格と言われております。
先ほどのFP技能士との違いとして、AFPは2年ごとに資格の更新が必要となり、更新するためにはセミナーや学習会・eラーニングなどにより一定以上の単位を取得する必要があります。
② AFPになるには?
AFPとして登録するために、以下の3つのルートがあります。
AFP認定研修(基本課程)の修了⇒FP2級合格
*認定研修を修了すると、FP3級に合格していなくても、FP2級の受験資格が得られます。
ルート2
2年以上の実務経験orFP3級合格⇒FP2級合格⇒AFP認定研修(技能士課程)の修了
ルート3
2年以上の実務経験orFP3級合格⇒AFP認定研修(基本課程)の修了+FP2級合格
つまり、AFPに登録するためには、「AFP認定研修の修了」と「FP2級合格」の2つの要件が必要となります。
③ AFPの難易度
上述のAFPになるためのルートを見ていただければわかる通り、AFPの難易度は、実質的にはFP2級の難易度と同様と言えます。
④ AFPのメリット
AFP取得のメリットとしては、以下が挙げられます。
・CFPを受験できる。(CFP資格審査試験の受験資格がAFP合格であるため。)
・資格更新のための継続的な知識のキャッチアップにより、FPとしてのスキルを維持できる。
・FP協会主催の学習会に参加でき、AFP同士の横のつながりができる。
FP講座の元運営責任者が、以下の7つの通信講座を比較して、おすすめ4つのメリット・デメリットや、講座の特徴について解説してみました。
・TAC
・大原
・LEC
・ユーキャン
・フォーサイト
・アーティス
・ECC
詳細は「FPの通信講座おすすめ4選:FP講座の元運営責任者が解説します!」をご確認ください。
4) CFPとは?
① CFPとは?
CFPはFP技能士1級に相当する資格と言われております。
AFP同様に2年ごとの資格の更新があり、一定以上の単位取得が要件とされております。
② CFPになるには?
CFPになるには、以下の要件を満たす必要があります。
・CFP研修の修了。
・通算で3年以上の実務経験。
・年2回開催(6月・11月)
・1課目ずつの受験も可能
・受験資格:「AFP認定」または「協会指定大学院の所定課程修了」
・試験6課目:
① 金融資産運用設計
② 不動産運用設計
③ ライフプランニング・リタイアメントプランニング
④ リスクと保険
⑤ タックスプランニング
⑥ 相続・事業承継設計
③ CFPの難易度
CFP資格審査試験の過去の合格率は以下となります。
・金融資産:金融資産運用設計
・不動産:不動産運用設計
・ライフ:ライフプランニング・リタイアメントプランニング
・リスク:リスクと保険
・タックス:タックスプランニング
・相続:相続・事業承継設計
2023年第2回
| 課目名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 金融資産 | 3,166 | 1,056 | 33% |
| 不動産 | 2,509 | 955 | 38% |
| ライフ | 2,530 | 895 | 35% |
| リスク | 3,126 | 1,104 | 35% |
| タックス | 2,590 | 923 | 36% |
| 相続 | 3,051 | 1,048 | 34% |
2023年第1回
| 課目名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 金融資産 | 3,615 | 1,111 | 31% |
| 不動産 | 2,575 | 921 | 36% |
| ライフ | 2,722 | 970 | 36% |
| リスク | 3,216 | 1,024 | 32% |
| タックス | 2,923 | 1,141 | 39% |
| 相続 | 3,329 | 1,045 | 31% |
2022年第2回
| 課目名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 金融資産 | 3,188 | 1,000 | 31% |
| 不動産 | 2,522 | 972 | 39% |
| ライフ | 2,630 | 968 | 37% |
| リスク | 3,301 | 1,194 | 36% |
| タックス | 2,729 | 1,001 | 37% |
| 相続 | 2,817 | 1,083 | 38% |
2022年第1回
| 課目名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 金融資産 | 3,628 | 1,245 | 34% |
| 不動産 | 2,687 | 996 | 37% |
| ライフ | 2,972 | 1,066 | 36% |
| リスク | 3,511 | 1,221 | 35% |
| タックス | 2,982 | 1,074 | 36% |
| 相続 | 3,169 | 1,262 | 40% |
2021年第2回
| 課目名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 金融資産 | 3,752 | 1,389 | 37% |
| 不動産 | 3,028 | 1,073 | 35% |
| ライフ | 3,056 | 1,169 | 38% |
| リスク | 3,673 | 1,506 | 41% |
| タックス | 3,118 | 1,169 | 38% |
| 相続 | 3,221 | 1,127 | 35% |
2021年第1回
| 課目名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 金融資産 | 4,305 | 1,501 | 35% |
| 不動産 | 2,918 | 1,033 | 35% |
| ライフ | 3,138 | 1,136 | 36% |
| リスク | 3,900 | 1,494 | 38% |
| タックス | 3,380 | 1,253 | 37% |
| 相続 | 3,277 | 1,188 | 36% |
30%~40%の合格率となり、一見そこまで難しくないようにも見えます。
しかし、受験者が全員AFP認定者、つまりFP2級合格者と考えると、そのうち4割しか受からない試験ですので、かなりの難関資格と言えます。
④ CFPのメリット
CFP取得のメリットとしては、以下が挙げられます。
・FPとして独立してやっていくのに十分な知識がつく。
・金融コンサルタントとして活躍できる。
・FPとしての力量を客観的に証明できる。
アメリカでは医師や弁護士と並んで、FPは専門家として重要視されております。
個人の資産運用がメインの仕事であり、平均年収は一説では2,000万円とも言われるほど、高給取りとなります。
日本でも今後個人の資産運用がさらに重要視され、FPの重要性が高まってくると考えられますので、今のうちからCFPとして実績を積んでおくのも1つの方向性です。
2. どの順番で取得する?
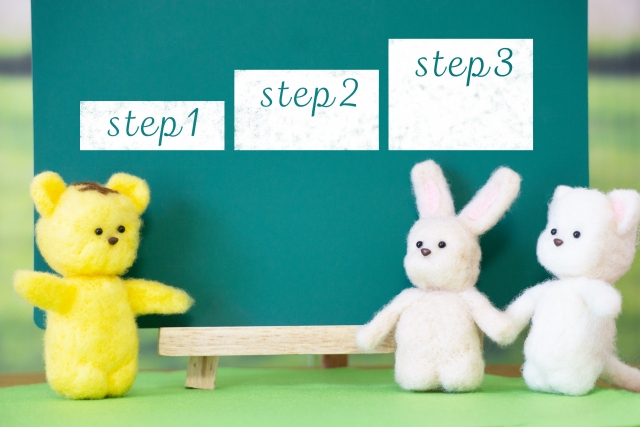
1) まずはFP2級合格を目指す
いずれのルートを目指すにしろ、まずはFP2級の合格を目指してください。
FP2級であれば一度取得してしまえば、永久的に資格を保持できます。
プライベートでライフプラン設計や株式投資などのためにFPを取得するのであれば、2級までで問題ございません。
2) 専門家を目指すのであればFP1級を取得
金融の専門家として金融機関や独立して活躍したいのであれば、とりあえずFP1級までの取得を目指してください。
CFPは更新が必要ですので、何かライフイベント(出産・子育て・病気・介護など)が発生した場合、資格を更新できなくなってしまいます。
そのためまずは、CFPと同程度の力量を証明できるFP1級に合格しておけば、何かあった際も資格を失効することなく、セーフティーネットとして安心です。
FP1級に合格できる実力があれば、CFP試験は独学でも十分合格可能であるため、FP1級合格後に必要に応じて挑戦してみてください。
3. 終わりに

FP技能士・AFP・CFPの違いについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
いずれにしろ、まずはFP技能士2級の合格を目指す必要があります。
そのうえで、自身のキャリアプランに応じて、自身が取得すべき資格を見極めてください。
4. まとめ
◆AFP・CFPはFP協会が主催する民間資格。
◆「FP技能士2級≒AFP」「FP技能士1級≒CFP」
◆まずはFP技能士2級の合格を目指す。